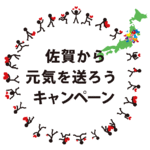2013年2月11日~12日に、アラブ首長国連邦(UAE)のドバイで初めての「世界政府サミットinUAE」が開催される。
国家、地域および国際的な政府の指導者や専門家を招き、アラブ首長国連邦(UAE)の連邦および地方政府機関を代表2000名が参加して開催される。
その中で佐賀県は日本から唯一、優れた行政機関として招待を受けた。
代表者の3名は公式ホームページにゲストスピーカーとして掲載された。
佐賀県とUAEとの絆は今でも確り繋がっています!(^^)!

国連公共サービス賞ワークショップ2:ネットワークとパートナーシップを形成する上でのイノベーション

川島氏は国連公共サービス賞の受賞を先頭で指揮した。
川島氏は『イノベーション”さが”プロジェクト』を含めた全体像を総括してプレゼンする。

藤崎氏は佐賀県の紹介と、佐賀県プロモーションDVD『TRHEE MINUTE TRIP TO SAGA』 の現担当としての話しをする。

山田氏は協働化テストへの携わってきた現場経験を行政&CSOの立場で話す。

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
佐賀県が招待を受けた理由は、2010年に公共サービスに関し最も権威ある国際表彰の「国連公共サービス賞」を日本で始めて受賞したからだ。
それも2部門で受賞し、それぞれ1位と2位の栄冠を納めた。
◎「政策策定過程への参加を促す革新的メカニズム」部門 第1位
「協働化テスト」
◎「政府内の知識管理促進」部門 第2位
「イノベーション”さが”プロジェクト」
これは本当に素晴らい栄冠を日本国民は勿論、佐賀県人も知る人が少ない。
もっとPRすべきだと強く感じます。
・国連行政ネットワーク(UNPAN)ホームページ
2010年国連公共サービスデー - 授賞式とフォーラム
http://www.unpan.org/DPADM/UNPSDayAwards/UNPublicServiceDay/2010PublicServiceDay/tabid/1306/language/en-US/Default.aspx
・総務省ホームページ
佐賀県が日本で初めて「国連公共サービス賞」を受賞
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02gyosei04_02000017.html
・外務省ホームページ
佐賀県の「2010年国連公共サービス賞」の受賞
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/22/5/0519_01.html
・佐賀県ホームページ
佐賀県が日本で初めて「国連公共サービス賞」を受賞
http://www.pref.saga.lg.jp/web/kensei/_1363/jyusyou.html
日本橋三越本店のサンフルーツさんの店舗に佐賀産ハウスみかんが登場!
サンフルーツさんは大正14年から続く青果物流業界の先駆者です。
そのサンフルーツさんが国内一押しのハウスみかんとして日本橋三越本店に置いて下さっています。
佐賀は日本一の生産量を誇るハウスみかんの産地です。
量だけではなく、品質もトップクラス!!
是非、ご賞味下さい<(_ _)>

サンフルーツさんは大正14年から続く青果物流業界の先駆者です。
そのサンフルーツさんが国内一押しのハウスみかんとして日本橋三越本店に置いて下さっています。
佐賀は日本一の生産量を誇るハウスみかんの産地です。
量だけではなく、品質もトップクラス!!
是非、ご賞味下さい<(_ _)>

きめ細かでニーズに即した提案型CSO活動を全県に拡大させる事は、CSOサポーターにとって命題とも言えるミッションです。
そのために、現実の壁に挫折しそうに成りながらも歯を食いしばって、私たちCSOサポーターは頑張っています。
そんな中、今朝の佐賀新聞1面記事には多少報われた気がしました。
今後も苦難の道は続きますが、頑張って業務に励もうと決意を新たにたところです。
※佐賀県庁HP:市民活動
※佐賀県庁HP:CSO提案型協働創出事業とは
※CSO-Portal (CSO情報をワンストップでお知らせ)
CSOとは:Civil Society Organizations(市民社会組織)の略で、NPO法人、市民活動・ボランティア団体に限らず、婦人会、老人会、PTAといった組織・団体も含めて「CSO」と呼称しています。
そのために、現実の壁に挫折しそうに成りながらも歯を食いしばって、私たちCSOサポーターは頑張っています。
そんな中、今朝の佐賀新聞1面記事には多少報われた気がしました。
今後も苦難の道は続きますが、頑張って業務に励もうと決意を新たにたところです。
※佐賀県庁HP:市民活動
※佐賀県庁HP:CSO提案型協働創出事業とは
※CSO-Portal (CSO情報をワンストップでお知らせ)
CSOとは:Civil Society Organizations(市民社会組織)の略で、NPO法人、市民活動・ボランティア団体に限らず、婦人会、老人会、PTAといった組織・団体も含めて「CSO」と呼称しています。
平成21年10月9日に開かれた「第27回全国地域づくり団体研修交流会・佐賀大会」の実行委員会も12回目。会場は佐賀市の「アバンセ(佐賀県立男女共同参画センター・佐賀県立生涯学習センター) 」でした。今回は大会の全体像も決まり、今後は全国の地域づくり団体への告知についてが議題となりました。

パンフレットも完成して全分科会に割り当て部数が配布されました。やはり完成品を見ると、いよいよだなーと感慨深いものです。このパンフレットの他に呼びかけ用のチラシも6,000部作成され、全国に配布されます。
参加募集の最終期限は平成21年11月30日ですが、11月11日に中間報告が発表されるそうです。我が分科会にどれ位の募集が有るか、興味津々と言ったところです。
また、参加者へのアンケートは本部を通して行う事となっています。各分科会では予算や運営内容など、細かい点が今後の協議内容となります。
パンフレット抜粋




議事
(1)佐賀大会参加者募集案内(お披露目)について
(2)佐賀大会参加呼びかけチラシ(案)について
(3)佐賀大会全体進行シナリオ(案)について
(4)その他

パンフレットも完成して全分科会に割り当て部数が配布されました。やはり完成品を見ると、いよいよだなーと感慨深いものです。このパンフレットの他に呼びかけ用のチラシも6,000部作成され、全国に配布されます。
参加募集の最終期限は平成21年11月30日ですが、11月11日に中間報告が発表されるそうです。我が分科会にどれ位の募集が有るか、興味津々と言ったところです。
また、参加者へのアンケートは本部を通して行う事となっています。各分科会では予算や運営内容など、細かい点が今後の協議内容となります。
パンフレット抜粋




「なんにもねぇ~♪」と地元お笑い芸人はなわ歌ってましたが、佐賀にはプロサッカーチームが有ります。
まだ、J2ですが…。
しかし最近は3連勝して、今までに無く気合が入っています。
勝点73、得失点差+18で5位に付けています。
残り試合が9ゲームと残り少なくなって、J1昇格には中々厳しいところです。
そのサガン鳥栖の最後のホームゲーム3試合が、鳥栖スタジアムのメンテナンスの関係で、場所を佐賀県総合運動場陸上競技場に移して行われます。
今まで応援に行きたくても、鳥栖は遠いと二の足を踏んでいた、県西北部の方々も会場が近くなります。
是非、佐賀県からJ1チームを送り出すために応援をお願いします。
まだ、J2ですが…。
しかし最近は3連勝して、今までに無く気合が入っています。
勝点73、得失点差+18で5位に付けています。
残り試合が9ゲームと残り少なくなって、J1昇格には中々厳しいところです。
そのサガン鳥栖の最後のホームゲーム3試合が、鳥栖スタジアムのメンテナンスの関係で、場所を佐賀県総合運動場陸上競技場に移して行われます。
10月 4日(日) 16:00 FC岐阜
10月18日(日) 16:00 ベガルタ仙台
10月25日(日) 12:30 ヴァンフォーレ甲府
今まで応援に行きたくても、鳥栖は遠いと二の足を踏んでいた、県西北部の方々も会場が近くなります。
是非、佐賀県からJ1チームを送り出すために応援をお願いします。
10月2日にNPO法人ハットウ・オンパクの野上泰生さんが来佐されます。
以前から告知していたオンパク研修in佐賀の第1回研修会のためにです。
どんな話が聞けるか、今からワクワクしています。
日時:10月2日(金) 13時~
場所:i-スクエアビル
i-スクエアビル
それに先駆けて野上さんの切なる希望で、前日の10月1日に武雄の餃子会館で餃子+ラーメン会を開催します。
こっちにも参加する予定です。
ホワイト・餃子店 餃子会館(武雄市)
路地裏散歩はまちづくりの第一歩


以前から告知していたオンパク研修in佐賀の第1回研修会のためにです。
どんな話が聞けるか、今からワクワクしています。
日時:10月2日(金) 13時~
場所:i-スクエアビル
i-スクエアビル
それに先駆けて野上さんの切なる希望で、前日の10月1日に武雄の餃子会館で餃子+ラーメン会を開催します。
こっちにも参加する予定です。
ホワイト・餃子店 餃子会館(武雄市)
路地裏散歩はまちづくりの第一歩


「がばい楽しか情報生活」と銘打って、唐津で200人(定員)規模のシニア向けパソコンセミナーが開催されます。
キーワードは"コミュニティ"です。今のパソコンは滅多に壊れませんし、正しく使えば危ない場所に繋がる事もありません。
参加は無料です。
さードンドン使って、新しい友達の“輪”を広げましょう ヽ( ´ ∇ ` )ノ
「がばい楽しか情報生活」
日 時 : 2009年5月22日(金) 13:00~14:30 (開場 12:30)
場 所 : 唐津市高齢者ふれあい会館 りふれ
(唐津市二タ子3丁目155-4)
講演内容 : 「デジタル文明開花を楽しむ処世術」
進 行 : ラーニングリーダーシップパートナーズ
青山 司、古賀 昭
定 員 : 200人(無料)
募集期限 : 5月15日(金)
主 催 : 佐賀県、マイクロソフト株式会社、佐賀県高度情報化推進協議会
後 援 : 佐賀新聞社、西日本新聞社、唐津市
協 力 : 高大唐津OB会、ラーニングリーダーシップパートナーズ
株式会社唐津ケーブルテレビジョン、財団法人佐賀県長寿社会振興財団
お問合せ : 佐賀県 統括本部 情報・業務改革課 地域情報推進担当
T E L:0952-25-7035
F A X:0952-25-7299
Email:jouhou-gyoumu@pref.saga.lg.jp

唐津市高齢者ふれあい会館りふれ MAP
キーワードは"コミュニティ"です。今のパソコンは滅多に壊れませんし、正しく使えば危ない場所に繋がる事もありません。
参加は無料です。
さードンドン使って、新しい友達の“輪”を広げましょう ヽ( ´ ∇ ` )ノ
「がばい楽しか情報生活」
日 時 : 2009年5月22日(金) 13:00~14:30 (開場 12:30)
場 所 : 唐津市高齢者ふれあい会館 りふれ
(唐津市二タ子3丁目155-4)
講演内容 : 「デジタル文明開花を楽しむ処世術」
進 行 : ラーニングリーダーシップパートナーズ
青山 司、古賀 昭
定 員 : 200人(無料)
募集期限 : 5月15日(金)
主 催 : 佐賀県、マイクロソフト株式会社、佐賀県高度情報化推進協議会
後 援 : 佐賀新聞社、西日本新聞社、唐津市
協 力 : 高大唐津OB会、ラーニングリーダーシップパートナーズ
株式会社唐津ケーブルテレビジョン、財団法人佐賀県長寿社会振興財団
お問合せ : 佐賀県 統括本部 情報・業務改革課 地域情報推進担当
T E L:0952-25-7035
F A X:0952-25-7299
Email:jouhou-gyoumu@pref.saga.lg.jp

唐津市高齢者ふれあい会館りふれ MAP
生産量日本一、味も全国トップクラスの佐賀県産ハウスミカン。その海外輸出向けブランド商標として「J-PON」(ジェイポン)を特許庁に商標登録申請していたのですが、登録拒絶されました。県は「認められなければ、これ以上争うつもりはない」としており、「JAや生産者と協議しながら決めていくことになる」と話しています。
駄目な物を何時までも悔やんでも仕方有りません。新しいブランド名を考えないといけません。今後は新しいブランド名の募集されるかも知れませんね。
その時は皆様、宜しくお願いします m(;_ _)m




駄目な物を何時までも悔やんでも仕方有りません。新しいブランド名を考えないといけません。今後は新しいブランド名の募集されるかも知れませんね。
その時は皆様、宜しくお願いします m(;_ _)m



今日の医療分野では、レントゲンやCTと言いた放射線を利用する機器が多くあります。だからと言って医療用の放射線治療施設を、原子力発電所と一緒に語るのは非常に乱暴な事だとは思います。
しかし、佐賀県にとってはこの炭素線がん治療施設「九州先端医療がんセンター」(仮称)も、九州電力が関係した放射線施設と言えます。
※重粒子線がん治療について
(平成18年12月:文部科学省)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
九州先端医療がんセンター(仮称)開設に向けたアセンター・セッションの開催
佐賀県HP(2008/10/20)
 いまから4年半後の平成25年春、九州で初めての炭素線がん治療施設となる「九州先端医療がんセンター(仮称)」のオープンを目指しています。
いまから4年半後の平成25年春、九州で初めての炭素線がん治療施設となる「九州先端医療がんセンター(仮称)」のオープンを目指しています。
この実現に向け、10月7日(火曜日)に福岡市内にて、アセンター・セッション(賛同者の集いという意味です)を開催し、佐賀県および福岡県の経済界、医療界関係者など、約170人の方に参加いただきました。画像:アセンター・セッションの様子
当日は、まず古川知事より、本センターで炭素線(重粒子線)を使った治療を行うこと、この治療法はがん組織に集中的に放射線を照射しがん細胞を破壊するので体への負担や副作用が少ないこと、設置を予定している鳥栖市の交通利便性などについて資料を用いて説明がありました。
続いて、九州財界および医療関係者から祝詞を頂戴しました。
九州電力松尾会長からは、「この計画は九州にとって大変意義があり、物心両面において支援や協力を約束したい」と、県のプロジェクトに対して高い評価をいただきました。
また、炭素線がん治療で世界をリードする、独立行政法人放射線医学総合研究所・重粒子医科学センター鎌田センター長から、佐賀県が導入予定の次世代型照射装置や炭素線治療実績の推移についてご説明がありました。
※添付ファイル
(アセンター・セッション資料.pdf)
(知事発言内容.pdf)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
炭素線がん治療事業主体会社
九電、九電工、久光が設立 佐賀、用地買収や施設建設
西日本新聞(2009/03/12)
最先端の炭素線がん治療施設「九州先端医療がんセンター」(仮称)の佐賀県鳥栖市への誘致を進める同県は11日、九州電力、九電工(ともに福岡市)、久光製薬(鳥栖市)の3社が4月に事業主体となる特定目的会社(SPC)を設立すると明らかにした。九州初の炭素線がん治療施設は2013年春の開業を目指し、動きだした。
県によると、3社は計数千万円を出資しSPCを設立。SPCは用地買収や施設建設を進め、治療を担当する医療法人に土地建物を賃貸する。総事業費150億円のうち20億円は佐賀県が負担し、残る130億円は九州経済界から出資や寄付を募り、金融機関にも融資を依頼する。民間からの出資や寄付で80億‐100億円を確保したい考え。
計画では、患者数は年間800人を見込み、開業5年目での黒字化を目指している。
炭素線がん治療は外科手術をせずに体外照射でがん細胞を死滅させる最先端医療で、国内で治療できるのは千葉、兵庫両県の2カ所しかない。
しかし、佐賀県にとってはこの炭素線がん治療施設「九州先端医療がんセンター」(仮称)も、九州電力が関係した放射線施設と言えます。
※重粒子線がん治療について
(平成18年12月:文部科学省)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
九州先端医療がんセンター(仮称)開設に向けたアセンター・セッションの開催
佐賀県HP(2008/10/20)
 いまから4年半後の平成25年春、九州で初めての炭素線がん治療施設となる「九州先端医療がんセンター(仮称)」のオープンを目指しています。
いまから4年半後の平成25年春、九州で初めての炭素線がん治療施設となる「九州先端医療がんセンター(仮称)」のオープンを目指しています。この実現に向け、10月7日(火曜日)に福岡市内にて、アセンター・セッション(賛同者の集いという意味です)を開催し、佐賀県および福岡県の経済界、医療界関係者など、約170人の方に参加いただきました。画像:アセンター・セッションの様子
当日は、まず古川知事より、本センターで炭素線(重粒子線)を使った治療を行うこと、この治療法はがん組織に集中的に放射線を照射しがん細胞を破壊するので体への負担や副作用が少ないこと、設置を予定している鳥栖市の交通利便性などについて資料を用いて説明がありました。
続いて、九州財界および医療関係者から祝詞を頂戴しました。
九州電力松尾会長からは、「この計画は九州にとって大変意義があり、物心両面において支援や協力を約束したい」と、県のプロジェクトに対して高い評価をいただきました。
また、炭素線がん治療で世界をリードする、独立行政法人放射線医学総合研究所・重粒子医科学センター鎌田センター長から、佐賀県が導入予定の次世代型照射装置や炭素線治療実績の推移についてご説明がありました。
※添付ファイル
(アセンター・セッション資料.pdf)
(知事発言内容.pdf)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
炭素線がん治療事業主体会社
九電、九電工、久光が設立 佐賀、用地買収や施設建設
西日本新聞(2009/03/12)
最先端の炭素線がん治療施設「九州先端医療がんセンター」(仮称)の佐賀県鳥栖市への誘致を進める同県は11日、九州電力、九電工(ともに福岡市)、久光製薬(鳥栖市)の3社が4月に事業主体となる特定目的会社(SPC)を設立すると明らかにした。九州初の炭素線がん治療施設は2013年春の開業を目指し、動きだした。
県によると、3社は計数千万円を出資しSPCを設立。SPCは用地買収や施設建設を進め、治療を担当する医療法人に土地建物を賃貸する。総事業費150億円のうち20億円は佐賀県が負担し、残る130億円は九州経済界から出資や寄付を募り、金融機関にも融資を依頼する。民間からの出資や寄付で80億‐100億円を確保したい考え。
計画では、患者数は年間800人を見込み、開業5年目での黒字化を目指している。
炭素線がん治療は外科手術をせずに体外照射でがん細胞を死滅させる最先端医療で、国内で治療できるのは千葉、兵庫両県の2カ所しかない。
佐賀も新幹線負担増に応じず
2月13日15時20分
整備新幹線の計画で国が新たに求めている建設負担金の増額について、佐賀県の古川康知事は佐賀県内を通る予定の九州新幹線の2つのルートの増額には「現時点では反対だ」と述べ、納得できる説明がないかぎり、負担に応じない方針を示しました。
佐賀県内では、九州新幹線の整備計画のうち、鳥栖市内で鹿児島ルートの工事が進められているほか、武雄温泉と長崎県の諫早の間で長崎ルートの工事が進められ、佐賀県はそれぞれの区間の建設費の3分の1を負担することになっています。佐賀県によりますと、国土交通省から建設費は建設資材の高騰などによって、当初の計画より増える見込みだと連絡がありました。佐賀県の負担分がいくら増額になるかは具体的に示されなかったものの、鹿児島ルートの総額は当初の計画より790億円増えておよそ8920億円に、長崎ルートは200億円増えておよそ2800億円になる見通しだと説明があったということです。これについて、佐賀県の古川康知事は13日の会見で、「資材の高騰分は新たな財源を作ってカバーするという話だった。どうしていきなり地方の負担ということになるのか。現時点では増額には反対だ。もっときちんと説明していただきたい」と述べ、国から納得できる説明がないかぎり、増額分の支払いには応じない方針を示しました。整備新幹線の建設負担金の増額をめぐっては、12日、新潟県の泉田知事が今の段階では支払いに応じない方針を明らかにしています。
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
◎新幹線地元負担増「現時点では反対」 古川知事
佐賀新聞(2009年2月13日)
整備新幹線の建設費増加分について国が地元自治体に負担増を求めている問題で、古川康知事は13日、「説明が不十分で増額には反対」と、現状では要請に応じられないとの考えを明らかにした。現在、国や建設主体となる独立行政法人の鉄道・運輸機構に納得いく説明を求めているとしている。
古川知事は機構側から具体的な増加額などの説明はないとした上で、地元に求めるのではなく「(JRが国に払う施設)使用料などで対応すると思っている」との考えを示した。負担問題が表面化した昨年11月には、福岡、熊本、鹿児島の4県で、地元の負担増がないよう国に対して申し入れた。
整備新幹線をめぐっては、資材高騰などを理由に国が地元自治体に負担増を求めている。増加額は九州新幹線鹿児島ルート(博多-新八代)全体で約790億円、長崎ルート(武雄-諫早)全体では約200億円とされている。佐賀県の負担増加額は明らかになっていない。
県は09年度当初予算案には、増加分を含まない現在計画の予算枠内分として、鹿児島ルートで約45億3000万円、長崎ルートで約7億2700万円を計上している。
2月13日15時20分
整備新幹線の計画で国が新たに求めている建設負担金の増額について、佐賀県の古川康知事は佐賀県内を通る予定の九州新幹線の2つのルートの増額には「現時点では反対だ」と述べ、納得できる説明がないかぎり、負担に応じない方針を示しました。
佐賀県内では、九州新幹線の整備計画のうち、鳥栖市内で鹿児島ルートの工事が進められているほか、武雄温泉と長崎県の諫早の間で長崎ルートの工事が進められ、佐賀県はそれぞれの区間の建設費の3分の1を負担することになっています。佐賀県によりますと、国土交通省から建設費は建設資材の高騰などによって、当初の計画より増える見込みだと連絡がありました。佐賀県の負担分がいくら増額になるかは具体的に示されなかったものの、鹿児島ルートの総額は当初の計画より790億円増えておよそ8920億円に、長崎ルートは200億円増えておよそ2800億円になる見通しだと説明があったということです。これについて、佐賀県の古川康知事は13日の会見で、「資材の高騰分は新たな財源を作ってカバーするという話だった。どうしていきなり地方の負担ということになるのか。現時点では増額には反対だ。もっときちんと説明していただきたい」と述べ、国から納得できる説明がないかぎり、増額分の支払いには応じない方針を示しました。整備新幹線の建設負担金の増額をめぐっては、12日、新潟県の泉田知事が今の段階では支払いに応じない方針を明らかにしています。
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
◎新幹線地元負担増「現時点では反対」 古川知事
佐賀新聞(2009年2月13日)
整備新幹線の建設費増加分について国が地元自治体に負担増を求めている問題で、古川康知事は13日、「説明が不十分で増額には反対」と、現状では要請に応じられないとの考えを明らかにした。現在、国や建設主体となる独立行政法人の鉄道・運輸機構に納得いく説明を求めているとしている。
古川知事は機構側から具体的な増加額などの説明はないとした上で、地元に求めるのではなく「(JRが国に払う施設)使用料などで対応すると思っている」との考えを示した。負担問題が表面化した昨年11月には、福岡、熊本、鹿児島の4県で、地元の負担増がないよう国に対して申し入れた。
整備新幹線をめぐっては、資材高騰などを理由に国が地元自治体に負担増を求めている。増加額は九州新幹線鹿児島ルート(博多-新八代)全体で約790億円、長崎ルート(武雄-諫早)全体では約200億円とされている。佐賀県の負担増加額は明らかになっていない。
県は09年度当初予算案には、増加分を含まない現在計画の予算枠内分として、鹿児島ルートで約45億3000万円、長崎ルートで約7億2700万円を計上している。

10月17日(金)・18日(土)の2日間、佐賀で「第3回 地域SNS全国フォーラム」が開催されます!
■会場:
佐賀県立美術館ホール
佐賀城本丸記念館御座の間
佐賀県職員互助会館大会議室
地域SNSはミクシィなどの全国展開するSNSとは違い、地域密着型のSNSです。
メジャーSNSとは違った魅了があります。、
それは、よりフェイスtoフェイスな関係が築けます。
また、地域に密着した問題解決にも有効なツールです。
地域SNS全国フォーラムは、地域SNSの参加者・運営者などが全国から集結します。
今回は第3回大会で、第1回兵庫(2007年8月)、第2回横浜(2008年2月)で開催されました。
SNSに興味のある方、既に利用されている方、是非参加してネットでは味わえないリアルな交流を楽しんで下さい。
昨日の"sagaBizCafe"の講師は、NHKの「プロジェクトX」でも取り上げられました、吉野ヶ里遺跡発掘調査の第1人者七田忠昭さんです。
演題は「吉野ヶ里遺跡から佐賀をしる」
佐賀県教育庁 社会教育
文化財課 副課長 七田忠昭さん

考古学・歴史学好きな私にとって、ワクワクする内容でした。
講演後のディスカッションでは、案の定「邪馬台国」の話題となり大盛況でした。
講演の中で七田さんは、吉野ヶ里には多くの大陸系の人々が佐賀に来ていたこと。
そして吉野ヶ里やその周辺に大陸の先進文化を取り入れた、巨大な都市ネットーワークを形成していたことをお話くださいました。
吉野ヶ里歴史公園

以下は昏君の見解
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
これはもっと古い時代に日本列島に渡来し定着していた、ネイティブ日本人との接触があった事を物語る。
最近のミトコンドリアDNAの分布研究からも、日本人が大雑把に「縄文系」と「弥生系」の混血であることを示している。
首都圏は「弥生系」が7割を占め、逆に東北や南九州で「縄文系」割合が高い。
このことは恐らく武力的な衝突も伴った、住み分けと考えられる。
母方のルーツでみる各地域集団の
縄文系と弥生系の割合

しかし北部九州にはこの解釈では説明出来ない、特殊な傾向がある。
「縄文系」と「弥生系」がほぼ同じ割合で分布するのだ。
これはもしかすると北部九州では、共存共栄が成功したのではないだろうか。
吉野ヶ里はそれの具現都市ではなかったか。
確かに佐賀市周辺の平野部と、唐津周辺の湾岸部の住み分け傾向は見られる。
だが、これは敵対的関係では無く、交流を伴った文化圏的住み分けだと思いたい。
現在、韓国の人たちのと軋轢が多方面で見られる。
確かにお互いを100%理解することは出来ない。
だが、妥協点を探り、協調し合うことは必ずしも不可能ではないと思う。
今後、吉野ヶ里の研究が進み古代の人々の交流の実態が明らかになり、日本・韓国の相互の理解の助けとなるこを期待したい。
演題は「吉野ヶ里遺跡から佐賀をしる」
佐賀県教育庁 社会教育
文化財課 副課長 七田忠昭さん

考古学・歴史学好きな私にとって、ワクワクする内容でした。
講演後のディスカッションでは、案の定「邪馬台国」の話題となり大盛況でした。
講演の中で七田さんは、吉野ヶ里には多くの大陸系の人々が佐賀に来ていたこと。
そして吉野ヶ里やその周辺に大陸の先進文化を取り入れた、巨大な都市ネットーワークを形成していたことをお話くださいました。
吉野ヶ里歴史公園

以下は昏君の見解
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
これはもっと古い時代に日本列島に渡来し定着していた、ネイティブ日本人との接触があった事を物語る。
最近のミトコンドリアDNAの分布研究からも、日本人が大雑把に「縄文系」と「弥生系」の混血であることを示している。
首都圏は「弥生系」が7割を占め、逆に東北や南九州で「縄文系」割合が高い。
このことは恐らく武力的な衝突も伴った、住み分けと考えられる。
母方のルーツでみる各地域集団の
縄文系と弥生系の割合

しかし北部九州にはこの解釈では説明出来ない、特殊な傾向がある。
「縄文系」と「弥生系」がほぼ同じ割合で分布するのだ。
これはもしかすると北部九州では、共存共栄が成功したのではないだろうか。
吉野ヶ里はそれの具現都市ではなかったか。
確かに佐賀市周辺の平野部と、唐津周辺の湾岸部の住み分け傾向は見られる。
だが、これは敵対的関係では無く、交流を伴った文化圏的住み分けだと思いたい。
現在、韓国の人たちのと軋轢が多方面で見られる。
確かにお互いを100%理解することは出来ない。
だが、妥協点を探り、協調し合うことは必ずしも不可能ではないと思う。
今後、吉野ヶ里の研究が進み古代の人々の交流の実態が明らかになり、日本・韓国の相互の理解の助けとなるこを期待したい。
佐賀県で唯一の「丸坊主」中学校が廃止されます。
私の通学生の頃は男子中学生は全員「丸坊主」、はっきり言って嫌でした。
ですから高校生になって髪が伸ばせて、本当にい嬉しかった思い出が有ります。
でもイザ無くなるとなると、寂しいですね。
オジサンにノスタルジーでしょうかね。
◎佐賀新聞(2008/01/19)
川副中、県内唯一の丸刈り規定30年ぶり廃止
佐賀市の川副中(村上良秀校長、481人)は、県内中学で唯一続けてきた男子の丸刈りを廃止した。「恥ずかしい」「髪形を選びたい」。そんな生徒の思いをくんだ約30年ぶりの頭髪の自由。見直しを主張した3年生の卒業式前に学校側が応えた。
川副中は1979年、「非行の未然防止策」として丸刈りを導入。当時、喫煙や飲酒など問題行為が頻発していた。「外見で大人と区別をつけることで、生徒に自制を促し、周囲も注意できる」。他校が人権や個性重視を理由に取りやめる中、継続してきた。
存廃についての論議は何度となく校内外であり、昨年5月の生徒総会であらためて、ある3年のクラスが「長髪を認めてほしい」と要望した。
それを受け、当時の生徒会が学校との協議を開始。秋には全校生徒と教職員を対象に賛否を問うアンケートをとった。「伝統を守るべき」という声があった一方で、「時代的におかしい」「丸刈りの中学には通いたくないという小学生がいる」など、廃止を求める意見が9割近くに上った。
学級討議や生徒集会も開いた。他校の校則を調べ、丸刈り規定を「中学生らしい清潔感のある髪形」に改正する案も作成。今月9日の臨時生徒総会で決議した。
学校側も並行して対応を検討し、PTAとの協議も重ねた。その結果、丸刈り廃止を決定し、生徒と保護者に16日、伝えた。村上校長は「生徒たちの頑張りに、任せてもいいと思った」と話す。
かつて同校が「頭髪自由校」だったころを知る現PTA会長の江頭修さん(54)は「丸刈りは強制すべきではない。廃止には大賛成」と語る。
卒業式は3月14日。前生徒会役員の江島武君(14)、栗林宏次君(15)らは「今回のことで川中(かわちゅう)がまとまった」と話し、「いい雰囲気を引き継いでほしい」と後輩たちに願う。
【写真】丸刈り廃止に奔走した川副中の前生徒会メンバーら=佐賀市の同校

私の通学生の頃は男子中学生は全員「丸坊主」、はっきり言って嫌でした。
ですから高校生になって髪が伸ばせて、本当にい嬉しかった思い出が有ります。
でもイザ無くなるとなると、寂しいですね。
オジサンにノスタルジーでしょうかね。
◎佐賀新聞(2008/01/19)
川副中、県内唯一の丸刈り規定30年ぶり廃止
佐賀市の川副中(村上良秀校長、481人)は、県内中学で唯一続けてきた男子の丸刈りを廃止した。「恥ずかしい」「髪形を選びたい」。そんな生徒の思いをくんだ約30年ぶりの頭髪の自由。見直しを主張した3年生の卒業式前に学校側が応えた。
川副中は1979年、「非行の未然防止策」として丸刈りを導入。当時、喫煙や飲酒など問題行為が頻発していた。「外見で大人と区別をつけることで、生徒に自制を促し、周囲も注意できる」。他校が人権や個性重視を理由に取りやめる中、継続してきた。
存廃についての論議は何度となく校内外であり、昨年5月の生徒総会であらためて、ある3年のクラスが「長髪を認めてほしい」と要望した。
それを受け、当時の生徒会が学校との協議を開始。秋には全校生徒と教職員を対象に賛否を問うアンケートをとった。「伝統を守るべき」という声があった一方で、「時代的におかしい」「丸刈りの中学には通いたくないという小学生がいる」など、廃止を求める意見が9割近くに上った。
学級討議や生徒集会も開いた。他校の校則を調べ、丸刈り規定を「中学生らしい清潔感のある髪形」に改正する案も作成。今月9日の臨時生徒総会で決議した。
学校側も並行して対応を検討し、PTAとの協議も重ねた。その結果、丸刈り廃止を決定し、生徒と保護者に16日、伝えた。村上校長は「生徒たちの頑張りに、任せてもいいと思った」と話す。
かつて同校が「頭髪自由校」だったころを知る現PTA会長の江頭修さん(54)は「丸刈りは強制すべきではない。廃止には大賛成」と語る。
卒業式は3月14日。前生徒会役員の江島武君(14)、栗林宏次君(15)らは「今回のことで川中(かわちゅう)がまとまった」と話し、「いい雰囲気を引き継いでほしい」と後輩たちに願う。
【写真】丸刈り廃止に奔走した川副中の前生徒会メンバーら=佐賀市の同校

今回の「地域ITリーダー養成講座」テーマは、『SNS』。
講師は、兵庫県で地域SNS『ひょこむ』を運営する「こたつねこさん」こと和崎宏氏です。
和崎氏は地域コミュニケーション研究の第一人者の御一人です。
もう一方の講師は、佐賀新聞社の牛島清豪氏です。
牛島氏は全国でも珍しい新聞社が運営する、地域SNS『ひびの』のデジタル戦略チームサブリーダーです。
佐賀の『SNS』を語るのに、この講演を聴き逃す訳にはいきませんね。
「地域ITリーダー養成講座」(第4回)~佐賀から始める地域情報化~
ITを活用した様々な分野におけるサービスを作り出す地域ITリーダーの育成を目的として、地域ITリーダー育成事業「地域ITリーダー養成講座」第4回)を開催します。
今回は、地域SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)をテーマに地域活性化の具体的な実践事例の検討を行い、佐賀の先端ビジネスモデルについて考えます。
ひとつは、地元佐賀新聞社の地域SNS「ひびの」のお話です。
佐賀新聞社が運営する情報コミュニティサイト「ひびの」は、2006年10月に開設され、身の回りから世界の話題まで、あらゆる情報が行き交い、集まるプラットホームとして、ニュースサイトと生活情報サイトを連携させ、SNSをドッキングさせたしくみを作り、ニュース以外のコンテンツを充実させることに成功しています。開設から1年を経過したところですが、会員数はすでに8,000人を超え、今も進化を続けています。 今後、生活者、メディアを取り巻く「情報」の何がどう変わっていくのか、地方紙のWeb展開や、地域SNS「ひびの」内での事例を挙げながら、そのポテンシャルを探ります。
もうひとつは、地域SNS最前線の話題です。
人を繋ぐツールだったSNSが、舞台を地域にフォーカスすることで、連携型のプラットホームとして息づき始めました。ここでは、地域SNSの最前線で企画されているトピックを紹介するとともに、地域活性化のための具体的な実践事例を検討し、すぐにでも始められる佐賀の先端ビジネスモデルを参加者の皆様といっしょに考えます。
ぜひ、この機会に先進事例などを題材とした「地域ITリーダー養成講座」に奮ってご参加ください。
※ SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)とは、人と人とのつながりを促進・サポートする、コミュニティ型の会員制のサービス、またそういったサービスを提供するWebサイトのことで、登録制や招待制などの幾つかの仕組みがあります。
◆日時: 2008年 1月12日(土) 13:30 ~ 16:30
◆会場:佐賀市立図書館多目的ホール 佐賀市天神3丁目2番15号
◆主催:佐賀県
◆共催:佐賀大学
◆受講対象者:
県内の自治体、企業、団体、CSO活動などにおいて、積極的にIT(情報技術)を活用したいと考えている方 であれば、どなたでも受講できます。
◆定員:先着30名 (受講無料)
◆申込方法:別紙申込書に必要事項を御記入の上、平成20年1月11日(金)までにFAXしてください。
◆申込先:佐賀県情報・業務改革課 担当 江頭
電話 (0952) 25-7035、ファックス (0952) 25-7299
◆個人情報について
ご記入していただいた氏名・勤務先・部署(役職名)等の個人情報は、 この事業の運営管理のために利用し、それ以外の目的には一切使用しません。(第3者への提供もいたしません。)
- プログラム -
1月12日(土)
受付 13:00~
講演(1) 13:30 ~ 14:30
『 地方紙からみた地域SNSのポテンシャル』

講師 佐賀新聞社 デジタル戦略チーム
サブリーダー 牛島 清豪(うしじま・きよひで)氏
(講演概要)
昨今、新聞各社のWebサイトは、単なるニュースサイトからの脱皮を図ろうとしています。ニュースアグリゲーター、ソーシャルニュースなど新しいニュース価値を生み出すWebサービスが林立する中、各新聞社はどういったWeb戦略を展開しようとしているのでしょうか。インターネットがなかった時代も、情報の周りには人が集まりコミュニケーションを重ねました。そして、ここからシビックジャーナリズムが生まれ、様々なクチコミ情報が発信されました。インターネットという便利な道具を手にした今、生活者、メディアを取り巻く「情報」の何がどう変わっていくのか、地方紙のウェブ展開や、地域SNS「ひびの」内での事例を挙げながら、そのポテンシャルを探ります。
講演(2) 14:40~ 16:30
『 地域SNS最前線 』
~ 情報プラットホームが拓く地域コミュニケーションの未来 ~

講師 総務省地域情報化アドバイザー・インフォミーム株式会社
代表取締役 和崎 宏(わさき・ひろし)氏
(講演概要)
人を繋ぐツールだったSNSが、舞台を地域にフォーカスすることで、連携型のプラットホームとして息づき始めました。眠れる「地域力」を覚醒するソーシャル・キャピタルの役割を担いながら、「カーナビ」「地域通貨」「動画」「地デジ」など次々と新たな連携機能を実装する地域SNS。すでに単なる道具から信頼できるコミュニティメディア基盤としての拡大が期待されています。
地域SNS間連携のキーパーソンとして、地域SNSの最前線で企画されているトピックを紹介するとともに、それらを活用した地域活性化のための具体的な実践事例の検討を行います。すぐにでも始められる佐賀の先端ビジネスモデルを探りましょう!
◎関連リンク
情報コミュニティサイト「ひびの」
コミュニティ活動支援型地域SNS「ひょこむ」
佐賀市立図書館
◎添付ファイル
和崎 宏(わさき・ひろし)氏プロフィール(PDFファイル,24kbtye)
講座申込書(第4回)(PDFファイル,60kbtye)
講師は、兵庫県で地域SNS『ひょこむ』を運営する「こたつねこさん」こと和崎宏氏です。
和崎氏は地域コミュニケーション研究の第一人者の御一人です。
もう一方の講師は、佐賀新聞社の牛島清豪氏です。
牛島氏は全国でも珍しい新聞社が運営する、地域SNS『ひびの』のデジタル戦略チームサブリーダーです。
佐賀の『SNS』を語るのに、この講演を聴き逃す訳にはいきませんね。
「地域ITリーダー養成講座」(第4回)~佐賀から始める地域情報化~
ITを活用した様々な分野におけるサービスを作り出す地域ITリーダーの育成を目的として、地域ITリーダー育成事業「地域ITリーダー養成講座」第4回)を開催します。
今回は、地域SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)をテーマに地域活性化の具体的な実践事例の検討を行い、佐賀の先端ビジネスモデルについて考えます。
ひとつは、地元佐賀新聞社の地域SNS「ひびの」のお話です。
佐賀新聞社が運営する情報コミュニティサイト「ひびの」は、2006年10月に開設され、身の回りから世界の話題まで、あらゆる情報が行き交い、集まるプラットホームとして、ニュースサイトと生活情報サイトを連携させ、SNSをドッキングさせたしくみを作り、ニュース以外のコンテンツを充実させることに成功しています。開設から1年を経過したところですが、会員数はすでに8,000人を超え、今も進化を続けています。 今後、生活者、メディアを取り巻く「情報」の何がどう変わっていくのか、地方紙のWeb展開や、地域SNS「ひびの」内での事例を挙げながら、そのポテンシャルを探ります。
もうひとつは、地域SNS最前線の話題です。
人を繋ぐツールだったSNSが、舞台を地域にフォーカスすることで、連携型のプラットホームとして息づき始めました。ここでは、地域SNSの最前線で企画されているトピックを紹介するとともに、地域活性化のための具体的な実践事例を検討し、すぐにでも始められる佐賀の先端ビジネスモデルを参加者の皆様といっしょに考えます。
ぜひ、この機会に先進事例などを題材とした「地域ITリーダー養成講座」に奮ってご参加ください。
※ SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)とは、人と人とのつながりを促進・サポートする、コミュニティ型の会員制のサービス、またそういったサービスを提供するWebサイトのことで、登録制や招待制などの幾つかの仕組みがあります。
◆日時: 2008年 1月12日(土) 13:30 ~ 16:30
◆会場:佐賀市立図書館多目的ホール 佐賀市天神3丁目2番15号
◆主催:佐賀県
◆共催:佐賀大学
◆受講対象者:
県内の自治体、企業、団体、CSO活動などにおいて、積極的にIT(情報技術)を活用したいと考えている方 であれば、どなたでも受講できます。
◆定員:先着30名 (受講無料)
◆申込方法:別紙申込書に必要事項を御記入の上、平成20年1月11日(金)までにFAXしてください。
◆申込先:佐賀県情報・業務改革課 担当 江頭
電話 (0952) 25-7035、ファックス (0952) 25-7299
◆個人情報について
ご記入していただいた氏名・勤務先・部署(役職名)等の個人情報は、 この事業の運営管理のために利用し、それ以外の目的には一切使用しません。(第3者への提供もいたしません。)
- プログラム -
1月12日(土)
受付 13:00~
講演(1) 13:30 ~ 14:30
『 地方紙からみた地域SNSのポテンシャル』

講師 佐賀新聞社 デジタル戦略チーム
サブリーダー 牛島 清豪(うしじま・きよひで)氏
(講演概要)
昨今、新聞各社のWebサイトは、単なるニュースサイトからの脱皮を図ろうとしています。ニュースアグリゲーター、ソーシャルニュースなど新しいニュース価値を生み出すWebサービスが林立する中、各新聞社はどういったWeb戦略を展開しようとしているのでしょうか。インターネットがなかった時代も、情報の周りには人が集まりコミュニケーションを重ねました。そして、ここからシビックジャーナリズムが生まれ、様々なクチコミ情報が発信されました。インターネットという便利な道具を手にした今、生活者、メディアを取り巻く「情報」の何がどう変わっていくのか、地方紙のウェブ展開や、地域SNS「ひびの」内での事例を挙げながら、そのポテンシャルを探ります。
講演(2) 14:40~ 16:30
『 地域SNS最前線 』
~ 情報プラットホームが拓く地域コミュニケーションの未来 ~

講師 総務省地域情報化アドバイザー・インフォミーム株式会社
代表取締役 和崎 宏(わさき・ひろし)氏
(講演概要)
人を繋ぐツールだったSNSが、舞台を地域にフォーカスすることで、連携型のプラットホームとして息づき始めました。眠れる「地域力」を覚醒するソーシャル・キャピタルの役割を担いながら、「カーナビ」「地域通貨」「動画」「地デジ」など次々と新たな連携機能を実装する地域SNS。すでに単なる道具から信頼できるコミュニティメディア基盤としての拡大が期待されています。
地域SNS間連携のキーパーソンとして、地域SNSの最前線で企画されているトピックを紹介するとともに、それらを活用した地域活性化のための具体的な実践事例の検討を行います。すぐにでも始められる佐賀の先端ビジネスモデルを探りましょう!
◎関連リンク
情報コミュニティサイト「ひびの」
コミュニティ活動支援型地域SNS「ひょこむ」
佐賀市立図書館
◎添付ファイル
和崎 宏(わさき・ひろし)氏プロフィール(PDFファイル,24kbtye)
講座申込書(第4回)(PDFファイル,60kbtye)
概要
玄海町は九州北西部佐賀県の東松浦半島の中央に位置します。
西部は玄界灘に面し、遠くは壱岐対馬を望むことができ、北・東・南を唐津市に接し、リアス式の美しい海岸線は、玄海国定公園の一部を成し、対馬海流の恵みを受け海の幸が豊富で、釣りのメッカにもなっています。
昭和31年9月30日、旧値賀村、旧有浦村の合併によって玄海町が誕生、翌年、旧切木村の一部を編入し、現在の行政区となり、平成17年の国勢調査で人口 6,738人、面積36k㎡、産業別就業人口割合は、平成12年国勢調査で、第一次産業25.7%、第二次産業30.3%、第三次産業44.0%となっています。
昭和31年町村合併当時は、炭鉱労働者も多かったのですが、石炭から石油へとエネルギーの転換が進むにつれ、昭和40年春、町勢発展を願って原子力発電所の誘致が持ち上がり、昭和46年から発電所の建設が始まり、これまで減少していた人口は定着してきました。
また、電源三法交付金事業などにより、道路をはじめ各施設の整備が進み、経済的波及効果は大きいものがあります。
町名に由来する「玄界灘」は、全国でも有数の漁場として知られ、町内の外津(ほかわず)と仮屋の港で水揚げされる豊富な海の幸と、低い山が波状的に起伏する「上場台地(うわばだいち)」と呼ばれる玄武岩特有の丘陵性台地がもたらす豊穣な農産物が自慢です。
「豊かで住みよい魅力と活力のある町づくり」を目指しています。
気候
玄海町の気候は、対馬海峡を北上する対馬暖流の影響を受けて比較的温暖で、寒暖の差が少ない海洋性気候の特性があります。
この暖流が流れる玄界灘は全国でも有数の漁場として知られ、町内の外津と仮屋の港で水揚げされる豊富な海の幸と、海洋性気候がもたらす新鮮な農作物が自慢です。
地勢

玄海町は東経129度52分、北緯33度28分の佐賀県の北西部、東松浦半島の西部中央にあります。西は玄界灘に面し、遠く壱岐・対馬を望むことができ、北・東・南は唐津市に接し、リアス式の美しい海岸線は、玄海国定公園の一部を成しています。
東西約7キロ、南北9キロ、総面積36平方キロメートルで標高100~200メートルの低い山が波状的に起伏する「上場台地(うわばだいち)」と呼ばれる玄武岩特有の丘陵性台地となっています。
町章

町章の図案は、「玄海町」の「玄」の字を片仮名の「カ」と「イ」で丸く囲み、町名をデザインしたもので、町民の融和、結束、そして将来に向かっての飛躍、発展を表わしており、昭和58年5月7日に制定されました。
町花:さくら

さくらは春いっせいに一群となって開花し、快い景観を見せ町民に親しまれており、町花にふさわしいとして指定しました。
町木:けやき

けやきの成木は、高さが30メートルにも達し、枝は大きく、材質は堅く、木目は大変美しい。
町がこの木のように大きく発展することを願って指定しました。
玄海町は九州北西部佐賀県の東松浦半島の中央に位置します。
西部は玄界灘に面し、遠くは壱岐対馬を望むことができ、北・東・南を唐津市に接し、リアス式の美しい海岸線は、玄海国定公園の一部を成し、対馬海流の恵みを受け海の幸が豊富で、釣りのメッカにもなっています。
昭和31年9月30日、旧値賀村、旧有浦村の合併によって玄海町が誕生、翌年、旧切木村の一部を編入し、現在の行政区となり、平成17年の国勢調査で人口 6,738人、面積36k㎡、産業別就業人口割合は、平成12年国勢調査で、第一次産業25.7%、第二次産業30.3%、第三次産業44.0%となっています。
昭和31年町村合併当時は、炭鉱労働者も多かったのですが、石炭から石油へとエネルギーの転換が進むにつれ、昭和40年春、町勢発展を願って原子力発電所の誘致が持ち上がり、昭和46年から発電所の建設が始まり、これまで減少していた人口は定着してきました。
また、電源三法交付金事業などにより、道路をはじめ各施設の整備が進み、経済的波及効果は大きいものがあります。
町名に由来する「玄界灘」は、全国でも有数の漁場として知られ、町内の外津(ほかわず)と仮屋の港で水揚げされる豊富な海の幸と、低い山が波状的に起伏する「上場台地(うわばだいち)」と呼ばれる玄武岩特有の丘陵性台地がもたらす豊穣な農産物が自慢です。
「豊かで住みよい魅力と活力のある町づくり」を目指しています。
気候
玄海町の気候は、対馬海峡を北上する対馬暖流の影響を受けて比較的温暖で、寒暖の差が少ない海洋性気候の特性があります。
この暖流が流れる玄界灘は全国でも有数の漁場として知られ、町内の外津と仮屋の港で水揚げされる豊富な海の幸と、海洋性気候がもたらす新鮮な農作物が自慢です。
地勢

玄海町は東経129度52分、北緯33度28分の佐賀県の北西部、東松浦半島の西部中央にあります。西は玄界灘に面し、遠く壱岐・対馬を望むことができ、北・東・南は唐津市に接し、リアス式の美しい海岸線は、玄海国定公園の一部を成しています。
東西約7キロ、南北9キロ、総面積36平方キロメートルで標高100~200メートルの低い山が波状的に起伏する「上場台地(うわばだいち)」と呼ばれる玄武岩特有の丘陵性台地となっています。
町章

町章の図案は、「玄海町」の「玄」の字を片仮名の「カ」と「イ」で丸く囲み、町名をデザインしたもので、町民の融和、結束、そして将来に向かっての飛躍、発展を表わしており、昭和58年5月7日に制定されました。
町花:さくら

さくらは春いっせいに一群となって開花し、快い景観を見せ町民に親しまれており、町花にふさわしいとして指定しました。
町木:けやき

けやきの成木は、高さが30メートルにも達し、枝は大きく、材質は堅く、木目は大変美しい。
町がこの木のように大きく発展することを願って指定しました。


.jpg)