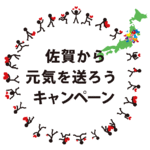町は取付道路の図面を作成していた。町は建設業者に仲介させて、取付道路の土地を個人で買って、個人で工事費を出し、個人で登記をさせようとしている。自分達は一切関したくないらしい。でもこの図面を見れば、明らかに公共事業に関連した取付道路にしか見えない。機能補償で処理すべき工事個所だ。
プルサーマル計画に伴う防災計画の避難道として機能する道路で、多くの税金が投入されている。それなのにどうして、こんな小さな取付道路が作れないのだろう。ますます納得いかない。
より大きな地図で 問題の取付道路個所 を表示
プルサーマル計画に伴う防災計画の避難道として機能する道路で、多くの税金が投入されている。それなのにどうして、こんな小さな取付道路が作れないのだろう。ますます納得いかない。
より大きな地図で 問題の取付道路個所 を表示
公共事業により田圃に入れなくなった。そのために取り付け道路を、個人で土地を買い、個人で工事を行い、個人で登記を行えと言われた。納得いかない。その道は、国内初のPluthermal計画の避難道として機能する。
エリカ様のお尻より、学生たちの柔軟な発想に賞賛!
<br/><a href="http://video.jp.msn.com/?mkt=ja-jp&from=&vid=00ebb149-2b1c-45d6-bb3c-e8d137ead6c1&fg=sharenoembed" target="_new"title="ブラジャー日本代表が決定!">ビデオ: ブラジャー日本代表が決定!</a>



◎NHKニュース佐賀県 公共サービスで受賞へ
5月19日 9時50分
国連が表彰している優れた公共サービスを行っている自治体や団体を選ぶ賞を、日本では初めて佐賀県が受賞することになりました。民間企業などからの提案を基に業務の外部委託を進めたことが、先進的と評価されました。
佐賀県が今回受賞するのは、国連の「公共サービス賞」で、優れた行政サービスを行っている自治体や団体を評価するため、7年前に創設されました。ことしは先月に最終審査が行われ、各国の専門家が4つの部門ごとに審査した結果、佐賀県が、行政と民間が協同で行う取り組みなどを評価する部門で最優秀賞に選ばれました。国連の公共サービス賞を受賞するのは、日本では佐賀県が初めてです。佐賀県などによりますと、今回の受賞では、県が4年前から行っている業務の外部委託の取り組みが先進的だと評価されたということです。佐賀県は、業務の内容をホームページなどで公開して、請負を希望する民間からの提案を幅広く受け付けていて、去年は県の文書を運ぶ業務を障害者の団体に委託するなど、4年間で業務の1割以上を外部に委託しました。表彰式は、国連公共サービスデーの来月23日、スペインのバルセロナで行われます。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20100519/k10014528261000.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

◎佐賀県が日本で初めて「国連公共サービス賞」を受賞
http://www.pref.saga.lg.jp/web/jyusyou.html

ゆるキャラを全国に売込むのが目的では無い。
全住民で地域の解決すべき優先課題を炙り出す事。
その課題に対して地域全体で考え、課題解決に向けた合意形成を作り出すのが目的。
ゆるキャラは切欠作りの道具。
http://scrumyobuko.sagafan.jp/e216553.html
全住民で地域の解決すべき優先課題を炙り出す事。
その課題に対して地域全体で考え、課題解決に向けた合意形成を作り出すのが目的。
ゆるキャラは切欠作りの道具。
http://scrumyobuko.sagafan.jp/e216553.html
肥前町、鎮西町、呼子町(共に現在は唐津市)と玄海町は、上場(うわば)四町と呼称されます。
それは火山活動によって形成された玄武岩の台地、『上場(うわば)台地』に位置するからです。
上場地区は複雑な地形であるために、耕地が階段状になっています。
いわゆる棚田や段々畑です。
そうして風化した玄武岩によって出来た『温石(おんじゃく)』と言う独特の土壌が特徴です。
この土は、柑橘類や水稲に向いているそうです。
実は地形条件は水稲に向いているのですが、上場地区は年間雨量が少ない干ばつ地帯でもありました。
そのために昔から溜池の多い地区でもあります。
上場開発による農地整備事業によって、松浦川から四つの農業用ダムへ貯水する事で水不足も解消されました。
この土壌と、棚田の地形による寒暖差が育む美味い米が『棚田コシヒカリ』です。
しかし、最近では別の問題が起こっています。
農家の後継者不足です。
また米価の全体下落は、いくら『棚田コシヒカリ』が多少高く売れても価格に限度があります。
この状態では平地より手間暇の掛かる棚田米では採算が取れず、人手を雇ってまで米作を行う農家はいません。
農家はハウスミカンやハウスイチゴの施設園芸や、玉ねぎなどの採算の合う産物への切り替えが進んでいます。
こんな状況ではありますが、農家が米を全く作らなくなった訳ではありません。
自分たちが食べる米位は作ります。
それに贅沢な話ですが、買った米は不味くて食べられないんですよね。
本当に贅沢ですよね…。
GWは昔から上場地区の農家に取って【田植え】の時期です。
休みなって全然関係ありません。
子供の頃、サラリーマンの子はGWを楽しみにしていましたが、農家の子は苦痛でしたね。
今は私が子供の頃に比べれば、機械化が進んで米作も楽になりました。
その分、慢性的な『機械貧乏』ですが…。
最近は減農薬が進んで、ホタルの幼虫のの餌の『カワニナ』が増えています。
その結果、ホタルの成虫も昔の様に増えてきました。
色んな意味で良い事ですよね。
ところで、カワニナの”ニナ”とは小さな巻貝を指す言葉です。
北部九州ではこの”ニナ”を”ミナ”と呼称します。
なので私たちはこの巻貝を『カワミナ』と呼んでいます。
それは火山活動によって形成された玄武岩の台地、『上場(うわば)台地』に位置するからです。
上場地区は複雑な地形であるために、耕地が階段状になっています。
いわゆる棚田や段々畑です。
そうして風化した玄武岩によって出来た『温石(おんじゃく)』と言う独特の土壌が特徴です。
この土は、柑橘類や水稲に向いているそうです。
実は地形条件は水稲に向いているのですが、上場地区は年間雨量が少ない干ばつ地帯でもありました。
そのために昔から溜池の多い地区でもあります。
上場開発による農地整備事業によって、松浦川から四つの農業用ダムへ貯水する事で水不足も解消されました。
この土壌と、棚田の地形による寒暖差が育む美味い米が『棚田コシヒカリ』です。
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
しかし、最近では別の問題が起こっています。
農家の後継者不足です。
また米価の全体下落は、いくら『棚田コシヒカリ』が多少高く売れても価格に限度があります。
この状態では平地より手間暇の掛かる棚田米では採算が取れず、人手を雇ってまで米作を行う農家はいません。
農家はハウスミカンやハウスイチゴの施設園芸や、玉ねぎなどの採算の合う産物への切り替えが進んでいます。
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
こんな状況ではありますが、農家が米を全く作らなくなった訳ではありません。
自分たちが食べる米位は作ります。
それに贅沢な話ですが、買った米は不味くて食べられないんですよね。
本当に贅沢ですよね…。
GWは昔から上場地区の農家に取って【田植え】の時期です。
休みなって全然関係ありません。
子供の頃、サラリーマンの子はGWを楽しみにしていましたが、農家の子は苦痛でしたね。
今は私が子供の頃に比べれば、機械化が進んで米作も楽になりました。
その分、慢性的な『機械貧乏』ですが…。
苗床から苗を運びます。
今年の苗は発育不良です。
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
最近は減農薬が進んで、ホタルの幼虫のの餌の『カワニナ』が増えています。
その結果、ホタルの成虫も昔の様に増えてきました。
色んな意味で良い事ですよね。
ところで、カワニナの”ニナ”とは小さな巻貝を指す言葉です。
北部九州ではこの”ニナ”を”ミナ”と呼称します。
なので私たちはこの巻貝を『カワミナ』と呼んでいます。
カワニナ又はカワミナ