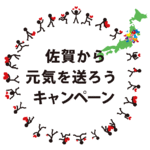現在の半導体はシリコン基板の上に形成されたいます。ここで電子の移動を起こす事で、複雑な回路を稼働させます。しかし、電子を利用した回路には限界が来ているそうです。
そこで登場するのが光子です。光子は電子と違って、互いに干渉することなく回路を行き来できるので、光チップなら2次元ではなく3次元での設計が出来ます。その結果、超高速化が可能です。
そうは分かっていても、光チップを実現するには「フォトニック結晶」と言う特殊な結晶が必要です。ダイヤモンドの結晶構造が理想的な「フォトニック結晶」だそうですが、密度が高すぎて利用出来ないとか。学者達も理想的な結晶構造が分からず、頭を悩ませていました。
所が思わぬ場所から、お手本とな結晶構造が見つかりました。何と昆虫の外殻からです。その昆虫はアマゾン原産の体長2、3センチの甲虫で、いわゆる玉虫色の光沢のある外殻を持っています。この甲虫の外殻を構成しているキチン質の分子構造が、進化の偶然から、光コンピューターを作るのに最適と考えられてきた構造になっていました。
これをお手本に、光チップを作ろうと言う事ですね。自然は時々、飛んでも無い事をやってのけます。まだまだ人間は、自然に学ぶべき所が多いと言う実例ですね。
学名Lamprocyphus augustusという甲虫

次世代の光チップ開発の鍵とな物質

そこで登場するのが光子です。光子は電子と違って、互いに干渉することなく回路を行き来できるので、光チップなら2次元ではなく3次元での設計が出来ます。その結果、超高速化が可能です。
そうは分かっていても、光チップを実現するには「フォトニック結晶」と言う特殊な結晶が必要です。ダイヤモンドの結晶構造が理想的な「フォトニック結晶」だそうですが、密度が高すぎて利用出来ないとか。学者達も理想的な結晶構造が分からず、頭を悩ませていました。
所が思わぬ場所から、お手本とな結晶構造が見つかりました。何と昆虫の外殻からです。その昆虫はアマゾン原産の体長2、3センチの甲虫で、いわゆる玉虫色の光沢のある外殻を持っています。この甲虫の外殻を構成しているキチン質の分子構造が、進化の偶然から、光コンピューターを作るのに最適と考えられてきた構造になっていました。
これをお手本に、光チップを作ろうと言う事ですね。自然は時々、飛んでも無い事をやってのけます。まだまだ人間は、自然に学ぶべき所が多いと言う実例ですね。
学名Lamprocyphus augustusという甲虫

次世代の光チップ開発の鍵とな物質