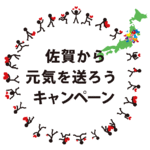◎タンポポの種類と分布調べよう 情報お待ちしています
在来種、外来種、雑種-など、タンポポの種類と分布を広域で調査するプロジェクトが、近畿以西で一斉に始まっている。5年に1回の調査で、ことし佐賀県も初めて参加。事務局では一般の協力を募り、寄せられた情報を研究に役立てるとともに、環境について考える機会にする。5月31日まで。
佐賀県内のタンポポは、ほとんどが明治以降の外来種。また、在来種も20以上に分かれていることが、最近になって判明している。
一般に、人の手による土地開発のあまり進んでいない場所には在来種が多く、在来種では花の下部の緑色の部分「総苞(そうぼう)」の外側が閉じ、外来種では開くことで見分けられるという。
県内のデータを取りまとめる西九州大子ども学部の上赤博文准教授は「県内の種類ごとの分布が初めて明らかになる」と意義を説き、「意外と研究が遅れている花なので、力を貸して」と調査協力を呼び掛ける。
タンポポを見つけたら調査用紙に場所や花の特徴を記入し、花の現物とともに所定の住所へ郵送する。花は専門家がDNA解析などで正確に分類。データをもとに分布地図も作り、ウェブサイトで公開する予定だ。
調査用紙は佐賀県立博物館などで配布、または「タンポポ調査2010」のサイトからダウンロードできる。問い合わせは上赤准教授、電話0952(31)3001へ。
佐賀新聞:2010年03月24日
在来種、外来種、雑種-など、タンポポの種類と分布を広域で調査するプロジェクトが、近畿以西で一斉に始まっている。5年に1回の調査で、ことし佐賀県も初めて参加。事務局では一般の協力を募り、寄せられた情報を研究に役立てるとともに、環境について考える機会にする。5月31日まで。
佐賀県内のタンポポは、ほとんどが明治以降の外来種。また、在来種も20以上に分かれていることが、最近になって判明している。
一般に、人の手による土地開発のあまり進んでいない場所には在来種が多く、在来種では花の下部の緑色の部分「総苞(そうぼう)」の外側が閉じ、外来種では開くことで見分けられるという。
県内のデータを取りまとめる西九州大子ども学部の上赤博文准教授は「県内の種類ごとの分布が初めて明らかになる」と意義を説き、「意外と研究が遅れている花なので、力を貸して」と調査協力を呼び掛ける。
タンポポを見つけたら調査用紙に場所や花の特徴を記入し、花の現物とともに所定の住所へ郵送する。花は専門家がDNA解析などで正確に分類。データをもとに分布地図も作り、ウェブサイトで公開する予定だ。
調査用紙は佐賀県立博物館などで配布、または「タンポポ調査2010」のサイトからダウンロードできる。問い合わせは上赤准教授、電話0952(31)3001へ。