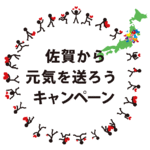「押し紙」って知っていますか?
販売店に持ち込まれる新聞は、配達時に新聞が濡れた時などに備える必要な「予備紙」が注文部数の2%まで認められているそうです。
しかし、実際にはそれを上回る(3~4割)もの配達されない新聞が持ち込まれいるとか。
これを「押し紙」と業界内では言うそうですが、新聞社は表向きには存在を認めていません。
この慣習はかなり昔から続いてようですが、要するに新聞社にとって、発行部数は広告を得るための重要な要素なのです。
広告主は多くの人に読まれている新聞に広告を載せたいと思います。
そのために部数を水増しして、見せ掛けの部数を増やしていたのです。
ただし、地方紙の場合、「押し紙」をしてでも大部数にみせかけ、広告の媒体価値を競い合う必要性は全国紙に比べて薄いようです。
そもそも販売店は新聞だけ配っていたのでは、儲けになりません。
新聞に差し込む折り込むチラシの収入で成り立っていました。
チラシの搬入枚数は、販売店が扱う新聞の総部数に準じるそうです。
部数が多いほどチラシ収入が多くなります。
また、新聞社が販売店へ補助金を支給していました。
つまりチラシの水増し収入と、押し紙で生じる損害を相殺するカラクリになっていました。
しかし、5~6年位前から様子が変わってきました。
新聞への広告掲載が減少してきたからです。
原因はダイレクトメール、フリーペーパーやインターネット広告にチラシの役割を奪われたからだと言われています。
また、広告主も新聞の広告効果に疑問を感じているようです。
それに、ニュースはTVとネットで十分だと考え、新聞を取らない人が増えれいます。
部数が減れば新聞社の販売店に対する補助金支給も、減っているのではないでしょうか。
これでは販売店はやって行けません。
自主廃業する販売店が増えたいます。
また「押し紙」の不公平さに対して訴訟を起こせケースも増えて、販売店が勝訴しているそうです。
この様な状況に対して新聞社も、新聞社側の資本も入った販売会社を増やして対抗しています。
しかし、現在のような販売店システムはこの先崩壊するのは目に見えています。
果たして、新聞社はどんな方策で生き残っていくのでしょうか?
山と積まれた配達されない新聞

販売店に持ち込まれる新聞は、配達時に新聞が濡れた時などに備える必要な「予備紙」が注文部数の2%まで認められているそうです。
しかし、実際にはそれを上回る(3~4割)もの配達されない新聞が持ち込まれいるとか。
これを「押し紙」と業界内では言うそうですが、新聞社は表向きには存在を認めていません。
この慣習はかなり昔から続いてようですが、要するに新聞社にとって、発行部数は広告を得るための重要な要素なのです。
広告主は多くの人に読まれている新聞に広告を載せたいと思います。
そのために部数を水増しして、見せ掛けの部数を増やしていたのです。
ただし、地方紙の場合、「押し紙」をしてでも大部数にみせかけ、広告の媒体価値を競い合う必要性は全国紙に比べて薄いようです。
そもそも販売店は新聞だけ配っていたのでは、儲けになりません。
新聞に差し込む折り込むチラシの収入で成り立っていました。
チラシの搬入枚数は、販売店が扱う新聞の総部数に準じるそうです。
部数が多いほどチラシ収入が多くなります。
また、新聞社が販売店へ補助金を支給していました。
つまりチラシの水増し収入と、押し紙で生じる損害を相殺するカラクリになっていました。
しかし、5~6年位前から様子が変わってきました。
新聞への広告掲載が減少してきたからです。
原因はダイレクトメール、フリーペーパーやインターネット広告にチラシの役割を奪われたからだと言われています。
また、広告主も新聞の広告効果に疑問を感じているようです。
それに、ニュースはTVとネットで十分だと考え、新聞を取らない人が増えれいます。
部数が減れば新聞社の販売店に対する補助金支給も、減っているのではないでしょうか。
これでは販売店はやって行けません。
自主廃業する販売店が増えたいます。
また「押し紙」の不公平さに対して訴訟を起こせケースも増えて、販売店が勝訴しているそうです。
この様な状況に対して新聞社も、新聞社側の資本も入った販売会社を増やして対抗しています。
しかし、現在のような販売店システムはこの先崩壊するのは目に見えています。
果たして、新聞社はどんな方策で生き残っていくのでしょうか?
山と積まれた配達されない新聞