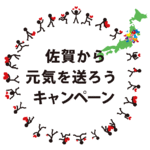J-CASTニュースに掲載された連載記事ですが、今後のメディアの在り方全般に言及した面白い記事なので紹介します。
記者クラブという「鎖国」制度 世界の笑いものだ
(連載「新聞崩壊」第1回/フリージャーナリストの上杉隆さんに聞く)
2008/12/30
北京の私服警官だらけの光景 新聞はどこまで伝えきれたのか
(連載「新聞崩壊」第2回/佐野眞一さんに新聞記者再生法を聞く)
2008/12/31
「変態記事」以降も毎日新聞の「ネット憎し」変わっていない
(連載「新聞崩壊」第3回/ITジャーナリスト・佐々木俊尚さんに聞く)
2009/1/ 1
新聞の20%以上は配達されない 「押し紙」という新聞社の「暗部」
(連載「新聞崩壊」第4回/フリージャーナリスト・黒薮哲哉さんに聞く)
2009/1/ 2
米国の新聞は決断した 「紙が減ってもウェブ中心でやる」
(連載「新聞崩壊」第5回/アルファブロガー・田中善一郎さんに聞く)
2009/1/ 3
新聞を法律で守る必要あるのか 「再販制」という反消費者制度
(連載「新聞崩壊」第6回/鶴田俊正名誉教授に聞く)
2009/1/ 4
人件費削るのは安易な方法 経営者はもっとビジョン示せ
(連載「新聞崩壊」第7回/新聞労連・一倉基益副委員長に聞く)
2009/1/ 5
「紙」にしがみつくほうが日本の新聞長生きできる
(連載「新聞崩壊」第8回/評論家・歌田明弘さんに聞く)
2009/1/ 6
新聞記者は会社官僚制の中で埋没 だから新しいニーズを掬えない
(連載「新聞崩壊」第9回/新聞研究者・林香里さんに聞く)
2009/1/ 7
ビジネスモデルが崩壊 身を削ぐような合理化が始まる
(連載「新聞崩壊」第10回/ジャーナリスト・河内孝さんに聞く)
2009/1/ 8
ネットで有名になり、新聞が売れる そんな好循環が中国では可能だ
(連載「新聞崩壊」第11回/中国メディア研究者 ミン大洪さんに聞く)
2009/1/ 9
再販、記者クラブ問題 新聞協会「当事者ではない」
(連載「新聞崩壊」第12回/新聞協会・新聞社の見解)
2009/1/13
記者クラブという「鎖国」制度 世界の笑いものだ
(連載「新聞崩壊」第1回/フリージャーナリストの上杉隆さんに聞く)
2008/12/30
北京の私服警官だらけの光景 新聞はどこまで伝えきれたのか
(連載「新聞崩壊」第2回/佐野眞一さんに新聞記者再生法を聞く)
2008/12/31
「変態記事」以降も毎日新聞の「ネット憎し」変わっていない
(連載「新聞崩壊」第3回/ITジャーナリスト・佐々木俊尚さんに聞く)
2009/1/ 1
新聞の20%以上は配達されない 「押し紙」という新聞社の「暗部」
(連載「新聞崩壊」第4回/フリージャーナリスト・黒薮哲哉さんに聞く)
2009/1/ 2
米国の新聞は決断した 「紙が減ってもウェブ中心でやる」
(連載「新聞崩壊」第5回/アルファブロガー・田中善一郎さんに聞く)
2009/1/ 3
新聞を法律で守る必要あるのか 「再販制」という反消費者制度
(連載「新聞崩壊」第6回/鶴田俊正名誉教授に聞く)
2009/1/ 4
人件費削るのは安易な方法 経営者はもっとビジョン示せ
(連載「新聞崩壊」第7回/新聞労連・一倉基益副委員長に聞く)
2009/1/ 5
「紙」にしがみつくほうが日本の新聞長生きできる
(連載「新聞崩壊」第8回/評論家・歌田明弘さんに聞く)
2009/1/ 6
新聞記者は会社官僚制の中で埋没 だから新しいニーズを掬えない
(連載「新聞崩壊」第9回/新聞研究者・林香里さんに聞く)
2009/1/ 7
ビジネスモデルが崩壊 身を削ぐような合理化が始まる
(連載「新聞崩壊」第10回/ジャーナリスト・河内孝さんに聞く)
2009/1/ 8
ネットで有名になり、新聞が売れる そんな好循環が中国では可能だ
(連載「新聞崩壊」第11回/中国メディア研究者 ミン大洪さんに聞く)
2009/1/ 9
再販、記者クラブ問題 新聞協会「当事者ではない」
(連載「新聞崩壊」第12回/新聞協会・新聞社の見解)
2009/1/13
非正規労働者と正規労働者に大きな格差が問題になっています。実は日本の労働市場の「二重性」を問題は、既に早い段階から指摘されていたのです。
今まではトヨタなどに代表されるように、輸出が良かったので表面化しませんでした。また、マスコミも其々の思惑から報道にバイアスを掛けていたようですね。
しかし、この世界的な景気後退の状況では、この問題がクローズアップせざろうえない状況です。
そんな中、日本の政局は止まっています。はっきり言って、国民はの殆どがウンザリしているでしょうね。
仮に総選挙か行われて民主党に政権が移っても、支持母体に労組系を多く持つ党です。この問題にどこまで踏み込めるかは、疑問を感じてしまいます。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
◎J-CAST(2009/1/14 )
「正社員の雇用保護は減らすべき」 「封印」されたOECD報告書
経済状況の悪化で「派遣切り」が問題化し、正社員のあり方が問われるなか、経済協力開発機構(OECD)の報告書で、非正規労働者と正規労働者に大きな格差がある日本の労働市場の「二重性」を問題視していることが分かった。さらに、待遇の差を縮小させるため「正規労働者の雇用保護を減少させるべきだ」とまで提言しているのだ。ところが、この報告書が提出された時期には、報告書について報じた記事は少なく、一般読者からすれば、ほぼ「封印」状態だった。
OECD加盟28か国のうち、10番目に「強く保護」
OECDは2008年春、日本経済の動向についてまとめた「対日経済審査報告書」を公表した。同報告書では、規制緩和や女性の就業促進を急ぐように勧告。6章あるうちの1章を、「加速する二重化と高齢化に対応するための労働市場の改革」と題し、日本の労働市場について割いている。
日本の労働力のうち、1985年には83.6%だった正規労働者の割合が、07年には66.3%にまで減少する一方、16.4%だった非正規労働者の割合は、07年には33.7%にまで増加。実に3人に1人以上が非正規労働者という計算だ。
このような現状に対して、「企業が非正規労働者を雇う、最も重要な理由は『労働コストを減らせるから』」という調査結果を紹介。
その背景として、
という分析だ。
報告書でも、時間(パートタイム)労働者の1時間あたりの賃金は、フルタイム労働者の4割に過ぎないし、非正規労働者を雇うことで、企業はボーナスや退職金の支払いを減らすことができる、などとしている。
正規労働者と非正規労働者との格差是正を求める
このような現状に対して、「勧告」されている内容が、国内で議論されている内容とは一線を画したものなのだ。報告書では、「加速する『労働市場の二重化』傾向を反転させる」という見出しが付いた上、(1)雇用の柔軟性を高める目的で(企業が)非正規労働者を雇う動機を少なくするため、正規労働者に対する雇用保護を減らす(2)非正規労働者のコスト面での利点を減らすために、非正規労働者に対する社会保障の適用範囲を広げる(3)人材育成や、非正規労働者の雇用可能性を高める、ことなどを勧告している。
さらに、OECDは、08年12月にも、日本の若年労働者(15~24歳)についての報告書を公表しており、その中でも
と指摘。そして、この現状に対して3項目が勧告されているが、そこにはこうある。
いずれの報告書でも、正規労働者と非正規労働者との格差是正を求める内容となっているが、正規労働者側に犠牲を求めるという点が共通している。日本の労働環境にとってはショッキングとも言える内容だが、日本国内の報道と見てみても、報告書について触れた記事は多くない。正社員保護についての論点に触れているのは、せいぜい日経新聞くらいだ。日経新聞のバックナンバーを調べてみると、
という記事で、報告書を作成するにあたっての途中経過を報じている。このほか、報告書が発表された時には、
という記事が掲載されている程度だ。
引き続き雇用情勢の悪化が避けられないとみられるなか、格差問題をどう扱うのかに注目が集まりそうだ。
今まではトヨタなどに代表されるように、輸出が良かったので表面化しませんでした。また、マスコミも其々の思惑から報道にバイアスを掛けていたようですね。
しかし、この世界的な景気後退の状況では、この問題がクローズアップせざろうえない状況です。
そんな中、日本の政局は止まっています。はっきり言って、国民はの殆どがウンザリしているでしょうね。
仮に総選挙か行われて民主党に政権が移っても、支持母体に労組系を多く持つ党です。この問題にどこまで踏み込めるかは、疑問を感じてしまいます。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
◎J-CAST(2009/1/14 )
「正社員の雇用保護は減らすべき」 「封印」されたOECD報告書
経済状況の悪化で「派遣切り」が問題化し、正社員のあり方が問われるなか、経済協力開発機構(OECD)の報告書で、非正規労働者と正規労働者に大きな格差がある日本の労働市場の「二重性」を問題視していることが分かった。さらに、待遇の差を縮小させるため「正規労働者の雇用保護を減少させるべきだ」とまで提言しているのだ。ところが、この報告書が提出された時期には、報告書について報じた記事は少なく、一般読者からすれば、ほぼ「封印」状態だった。
OECD加盟28か国のうち、10番目に「強く保護」
OECDは2008年春、日本経済の動向についてまとめた「対日経済審査報告書」を公表した。同報告書では、規制緩和や女性の就業促進を急ぐように勧告。6章あるうちの1章を、「加速する二重化と高齢化に対応するための労働市場の改革」と題し、日本の労働市場について割いている。
日本の労働力のうち、1985年には83.6%だった正規労働者の割合が、07年には66.3%にまで減少する一方、16.4%だった非正規労働者の割合は、07年には33.7%にまで増加。実に3人に1人以上が非正規労働者という計算だ。
このような現状に対して、「企業が非正規労働者を雇う、最も重要な理由は『労働コストを減らせるから』」という調査結果を紹介。
その背景として、
「日本はOECD加盟28か国のうち、10番目に、正規労働者に対する雇用保護が強い」と指摘している。つまり、「正規労働者が強く保護されている分、コストカットがしやすい非正規労働者が増えてきている」
という分析だ。
報告書でも、時間(パートタイム)労働者の1時間あたりの賃金は、フルタイム労働者の4割に過ぎないし、非正規労働者を雇うことで、企業はボーナスや退職金の支払いを減らすことができる、などとしている。
正規労働者と非正規労働者との格差是正を求める
このような現状に対して、「勧告」されている内容が、国内で議論されている内容とは一線を画したものなのだ。報告書では、「加速する『労働市場の二重化』傾向を反転させる」という見出しが付いた上、(1)雇用の柔軟性を高める目的で(企業が)非正規労働者を雇う動機を少なくするため、正規労働者に対する雇用保護を減らす(2)非正規労働者のコスト面での利点を減らすために、非正規労働者に対する社会保障の適用範囲を広げる(3)人材育成や、非正規労働者の雇用可能性を高める、ことなどを勧告している。
さらに、OECDは、08年12月にも、日本の若年労働者(15~24歳)についての報告書を公表しており、その中でも
「日本の若者は、日本の労働市場で加速する二重化の影響を大きく受けている」
「期間労働から定職に移行するのは困難で、多くの若者が、不安定な職に『はまり込んだ』状態になっている」
と指摘。そして、この現状に対して3項目が勧告されているが、そこにはこうある。
「正規労働者と非正規労働者との保護率の差を減らし、賃金や福利厚生面での差別的措置に対応する。この措置には、期間労働者に対する社会保障の適用範囲を拡大する一方、正規労働者に対する雇用保護を緩和することも含む」
いずれの報告書でも、正規労働者と非正規労働者との格差是正を求める内容となっているが、正規労働者側に犠牲を求めるという点が共通している。日本の労働環境にとってはショッキングとも言える内容だが、日本国内の報道と見てみても、報告書について触れた記事は多くない。正社員保護についての論点に触れているのは、せいぜい日経新聞くらいだ。日経新聞のバックナンバーを調べてみると、
「OEDD対日経済審査 女性の就業促進勧告へ」(08年1月22日)
という記事で、報告書を作成するにあたっての途中経過を報じている。このほか、報告書が発表された時には、
「日本の正社員 過保護? OECDが労働市場分析 『非正社員、処遇改善遅れ』」(08年3月5日)
という記事が掲載されている程度だ。
引き続き雇用情勢の悪化が避けられないとみられるなか、格差問題をどう扱うのかに注目が集まりそうだ。