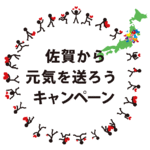非正規労働者と正規労働者に大きな格差が問題になっています。実は日本の労働市場の「二重性」を問題は、既に早い段階から指摘されていたのです。
今まではトヨタなどに代表されるように、輸出が良かったので表面化しませんでした。また、マスコミも其々の思惑から報道にバイアスを掛けていたようですね。
しかし、この世界的な景気後退の状況では、この問題がクローズアップせざろうえない状況です。
そんな中、日本の政局は止まっています。はっきり言って、国民はの殆どがウンザリしているでしょうね。
仮に総選挙か行われて民主党に政権が移っても、支持母体に労組系を多く持つ党です。この問題にどこまで踏み込めるかは、疑問を感じてしまいます。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
◎J-CAST(2009/1/14 )
「正社員の雇用保護は減らすべき」 「封印」されたOECD報告書
経済状況の悪化で「派遣切り」が問題化し、正社員のあり方が問われるなか、経済協力開発機構(OECD)の報告書で、非正規労働者と正規労働者に大きな格差がある日本の労働市場の「二重性」を問題視していることが分かった。さらに、待遇の差を縮小させるため「正規労働者の雇用保護を減少させるべきだ」とまで提言しているのだ。ところが、この報告書が提出された時期には、報告書について報じた記事は少なく、一般読者からすれば、ほぼ「封印」状態だった。
OECD加盟28か国のうち、10番目に「強く保護」
OECDは2008年春、日本経済の動向についてまとめた「対日経済審査報告書」を公表した。同報告書では、規制緩和や女性の就業促進を急ぐように勧告。6章あるうちの1章を、「加速する二重化と高齢化に対応するための労働市場の改革」と題し、日本の労働市場について割いている。
日本の労働力のうち、1985年には83.6%だった正規労働者の割合が、07年には66.3%にまで減少する一方、16.4%だった非正規労働者の割合は、07年には33.7%にまで増加。実に3人に1人以上が非正規労働者という計算だ。
このような現状に対して、「企業が非正規労働者を雇う、最も重要な理由は『労働コストを減らせるから』」という調査結果を紹介。
その背景として、
という分析だ。
報告書でも、時間(パートタイム)労働者の1時間あたりの賃金は、フルタイム労働者の4割に過ぎないし、非正規労働者を雇うことで、企業はボーナスや退職金の支払いを減らすことができる、などとしている。
正規労働者と非正規労働者との格差是正を求める
このような現状に対して、「勧告」されている内容が、国内で議論されている内容とは一線を画したものなのだ。報告書では、「加速する『労働市場の二重化』傾向を反転させる」という見出しが付いた上、(1)雇用の柔軟性を高める目的で(企業が)非正規労働者を雇う動機を少なくするため、正規労働者に対する雇用保護を減らす(2)非正規労働者のコスト面での利点を減らすために、非正規労働者に対する社会保障の適用範囲を広げる(3)人材育成や、非正規労働者の雇用可能性を高める、ことなどを勧告している。
さらに、OECDは、08年12月にも、日本の若年労働者(15~24歳)についての報告書を公表しており、その中でも
と指摘。そして、この現状に対して3項目が勧告されているが、そこにはこうある。
いずれの報告書でも、正規労働者と非正規労働者との格差是正を求める内容となっているが、正規労働者側に犠牲を求めるという点が共通している。日本の労働環境にとってはショッキングとも言える内容だが、日本国内の報道と見てみても、報告書について触れた記事は多くない。正社員保護についての論点に触れているのは、せいぜい日経新聞くらいだ。日経新聞のバックナンバーを調べてみると、
という記事で、報告書を作成するにあたっての途中経過を報じている。このほか、報告書が発表された時には、
という記事が掲載されている程度だ。
引き続き雇用情勢の悪化が避けられないとみられるなか、格差問題をどう扱うのかに注目が集まりそうだ。
今まではトヨタなどに代表されるように、輸出が良かったので表面化しませんでした。また、マスコミも其々の思惑から報道にバイアスを掛けていたようですね。
しかし、この世界的な景気後退の状況では、この問題がクローズアップせざろうえない状況です。
そんな中、日本の政局は止まっています。はっきり言って、国民はの殆どがウンザリしているでしょうね。
仮に総選挙か行われて民主党に政権が移っても、支持母体に労組系を多く持つ党です。この問題にどこまで踏み込めるかは、疑問を感じてしまいます。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
◎J-CAST(2009/1/14 )
「正社員の雇用保護は減らすべき」 「封印」されたOECD報告書
経済状況の悪化で「派遣切り」が問題化し、正社員のあり方が問われるなか、経済協力開発機構(OECD)の報告書で、非正規労働者と正規労働者に大きな格差がある日本の労働市場の「二重性」を問題視していることが分かった。さらに、待遇の差を縮小させるため「正規労働者の雇用保護を減少させるべきだ」とまで提言しているのだ。ところが、この報告書が提出された時期には、報告書について報じた記事は少なく、一般読者からすれば、ほぼ「封印」状態だった。
OECD加盟28か国のうち、10番目に「強く保護」
OECDは2008年春、日本経済の動向についてまとめた「対日経済審査報告書」を公表した。同報告書では、規制緩和や女性の就業促進を急ぐように勧告。6章あるうちの1章を、「加速する二重化と高齢化に対応するための労働市場の改革」と題し、日本の労働市場について割いている。
日本の労働力のうち、1985年には83.6%だった正規労働者の割合が、07年には66.3%にまで減少する一方、16.4%だった非正規労働者の割合は、07年には33.7%にまで増加。実に3人に1人以上が非正規労働者という計算だ。
このような現状に対して、「企業が非正規労働者を雇う、最も重要な理由は『労働コストを減らせるから』」という調査結果を紹介。
その背景として、
「日本はOECD加盟28か国のうち、10番目に、正規労働者に対する雇用保護が強い」と指摘している。つまり、「正規労働者が強く保護されている分、コストカットがしやすい非正規労働者が増えてきている」
という分析だ。
報告書でも、時間(パートタイム)労働者の1時間あたりの賃金は、フルタイム労働者の4割に過ぎないし、非正規労働者を雇うことで、企業はボーナスや退職金の支払いを減らすことができる、などとしている。
正規労働者と非正規労働者との格差是正を求める
このような現状に対して、「勧告」されている内容が、国内で議論されている内容とは一線を画したものなのだ。報告書では、「加速する『労働市場の二重化』傾向を反転させる」という見出しが付いた上、(1)雇用の柔軟性を高める目的で(企業が)非正規労働者を雇う動機を少なくするため、正規労働者に対する雇用保護を減らす(2)非正規労働者のコスト面での利点を減らすために、非正規労働者に対する社会保障の適用範囲を広げる(3)人材育成や、非正規労働者の雇用可能性を高める、ことなどを勧告している。
さらに、OECDは、08年12月にも、日本の若年労働者(15~24歳)についての報告書を公表しており、その中でも
「日本の若者は、日本の労働市場で加速する二重化の影響を大きく受けている」
「期間労働から定職に移行するのは困難で、多くの若者が、不安定な職に『はまり込んだ』状態になっている」
と指摘。そして、この現状に対して3項目が勧告されているが、そこにはこうある。
「正規労働者と非正規労働者との保護率の差を減らし、賃金や福利厚生面での差別的措置に対応する。この措置には、期間労働者に対する社会保障の適用範囲を拡大する一方、正規労働者に対する雇用保護を緩和することも含む」
いずれの報告書でも、正規労働者と非正規労働者との格差是正を求める内容となっているが、正規労働者側に犠牲を求めるという点が共通している。日本の労働環境にとってはショッキングとも言える内容だが、日本国内の報道と見てみても、報告書について触れた記事は多くない。正社員保護についての論点に触れているのは、せいぜい日経新聞くらいだ。日経新聞のバックナンバーを調べてみると、
「OEDD対日経済審査 女性の就業促進勧告へ」(08年1月22日)
という記事で、報告書を作成するにあたっての途中経過を報じている。このほか、報告書が発表された時には、
「日本の正社員 過保護? OECDが労働市場分析 『非正社員、処遇改善遅れ』」(08年3月5日)
という記事が掲載されている程度だ。
引き続き雇用情勢の悪化が避けられないとみられるなか、格差問題をどう扱うのかに注目が集まりそうだ。
この記事を読んで思う事。
こう言った研究は農業以外の医療分野などにも応用ができ、大いに研究すべきです。
ただ農業分野に関して言わせてもらえば。
高齢者をそこまでして作業従事させるより、車産業などの製造業の失業者を農業に回す事が一番合理的だ!
もっと国には就業者のコーディネートに、知恵とお金を使ってもらいたいものです。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
◎毎日新聞(2009年1月9日)
ロボットスーツ:農作業の負担軽減 東京農工大が開発
 大根抜きなど負担の大きな農作業を手助けする「農業ロボットスーツ」を東京農工大が開発し、9日東京都府中市のキャンパスで実演した。スーツの重さは約25キロだが、今後半分に軽量化し、2年後には50万~100万円で市販する計画だ。
大根抜きなど負担の大きな農作業を手助けする「農業ロボットスーツ」を東京農工大が開発し、9日東京都府中市のキャンパスで実演した。スーツの重さは約25キロだが、今後半分に軽量化し、2年後には50万~100万円で市販する計画だ。
公開された作業は▽イチゴ摘み▽ポンカンの剪定(せんてい)▽大根抜き--の3種類。長時間、腕を上げている剪定作業や腰を曲げるイチゴ摘みは体への負担が大きい。大根抜きでは腰に約30キロの力がかかる。
ロボットは肩やひじ、腰、ひざの関節に計8個のモーターを付け、作業者を補助する。大根抜きではスーツの装着で半分以下の力で済み、他の2種類でもほとんど負担を感じずに作業できたという。
現在、農業従事者の約4割が65歳以上で、補助ロボット開発を期待する声が高まっている。100台売れると1台約30万円に価格を下げることも可能といい、大学は上下半身で分けての販売も検討している。開発した遠山茂樹教授(ロボット工学)は「作業効率を落とさず、誰でも使うことができる。補助できる作業の種類を増やしたい」と話す。
こう言った研究は農業以外の医療分野などにも応用ができ、大いに研究すべきです。
ただ農業分野に関して言わせてもらえば。
高齢者をそこまでして作業従事させるより、車産業などの製造業の失業者を農業に回す事が一番合理的だ!
もっと国には就業者のコーディネートに、知恵とお金を使ってもらいたいものです。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
◎毎日新聞(2009年1月9日)
ロボットスーツ:農作業の負担軽減 東京農工大が開発
 大根抜きなど負担の大きな農作業を手助けする「農業ロボットスーツ」を東京農工大が開発し、9日東京都府中市のキャンパスで実演した。スーツの重さは約25キロだが、今後半分に軽量化し、2年後には50万~100万円で市販する計画だ。
大根抜きなど負担の大きな農作業を手助けする「農業ロボットスーツ」を東京農工大が開発し、9日東京都府中市のキャンパスで実演した。スーツの重さは約25キロだが、今後半分に軽量化し、2年後には50万~100万円で市販する計画だ。公開された作業は▽イチゴ摘み▽ポンカンの剪定(せんてい)▽大根抜き--の3種類。長時間、腕を上げている剪定作業や腰を曲げるイチゴ摘みは体への負担が大きい。大根抜きでは腰に約30キロの力がかかる。
ロボットは肩やひじ、腰、ひざの関節に計8個のモーターを付け、作業者を補助する。大根抜きではスーツの装着で半分以下の力で済み、他の2種類でもほとんど負担を感じずに作業できたという。
現在、農業従事者の約4割が65歳以上で、補助ロボット開発を期待する声が高まっている。100台売れると1台約30万円に価格を下げることも可能といい、大学は上下半身で分けての販売も検討している。開発した遠山茂樹教授(ロボット工学)は「作業効率を落とさず、誰でも使うことができる。補助できる作業の種類を増やしたい」と話す。
私の住む地区には、昔から正月七日に「鬼火焚き」を行う風習があります。昔は中学生と小学生だけで制作から、火の後始末まで全て行っていました。そして町内の全部が、地区別に同じ様に行っていました。名称も町内では『ヒョーケンギョー』と呼称しています。
最近では少子化の影響で、幾つかの地区は行っていません。私の地区の一時期、特に男の子が減ってこの行事は途切れていました。しかし、それではいけないと昔ヒョーケンギョーを作った親の世代が、子供たちと一緒に作る様になり復活しました。
伝統を守る事は大事ですが、昔の形に拘り過ぎると廃れてしまいます。守るべき所は確り守り、時代にそって変えるべき所は変えていかなければ続きません。
確かに変える場合は、大きな葛藤があり大変でしょう。でも、先人もそうやって受け継いできたのだと思います。ヒョーケンギョーも形を変えながらも、受け継いでいってもらいたい物です。
実は燃やしている場面も撮りたかったのですが、間に合わず朝撮った燃やす前の写真を添付します。これで御容赦を願います<(_ _)>
昔は高さ太さ共に大きかったですね。

正月に飾った角松やしめ飾り、古いお守の一緒に燃やす。

最近では少子化の影響で、幾つかの地区は行っていません。私の地区の一時期、特に男の子が減ってこの行事は途切れていました。しかし、それではいけないと昔ヒョーケンギョーを作った親の世代が、子供たちと一緒に作る様になり復活しました。
伝統を守る事は大事ですが、昔の形に拘り過ぎると廃れてしまいます。守るべき所は確り守り、時代にそって変えるべき所は変えていかなければ続きません。
確かに変える場合は、大きな葛藤があり大変でしょう。でも、先人もそうやって受け継いできたのだと思います。ヒョーケンギョーも形を変えながらも、受け継いでいってもらいたい物です。
実は燃やしている場面も撮りたかったのですが、間に合わず朝撮った燃やす前の写真を添付します。これで御容赦を願います<(_ _)>
昔は高さ太さ共に大きかったですね。

正月に飾った角松やしめ飾り、古いお守の一緒に燃やす。

佐賀県が主催し、モラージュ佐賀とさが棚田ネットワークが協力して開催された『平成20年度・農村風景フォトコンテスト』開催されていました。

さくら児童館からも撮り溜めた写真を、職員と、子ども達の写真の中から一枚ずつ出品していました。
その子ども達の写真が、「キッズ賞」に見事入選!

私は児童館に撮影に行った際には、子供たちに一眼レフカメラやビデオカメラを自由に使わせてみます。その場合には基本的な撮影方法だけ教えて、後は自由さえていて見ています。
この写真を撮ったのは女の子ですが、他の子どもに比べてセンスが良いなと常々思っていました。今回の写真を出品する際の選考に私うも立ち会ったのですが、この写真良いなと思い撮影者を聞いて「やっぱり」なと思った次第です。
この作品のタイトルは『そばの畑でかくれんぼ』ですが、多くの方が元ネタに気づかれたと思います。J・D・サリンジャーの『ライ麦畑でつかまえて』です。小説の内容と写真の状況は全く一致しませんが、大人たち全員がこのタイトルで納得してしまいました。子供ですから狙って撮った訳ではないでしょうが、先頭を歩いて来る男の子がイメージがぴったり過ぎて苦笑してしまいました。
入選作はモラージュ佐賀に08年12月末~09年1月上旬に展示されるそうですから、お暇の方は佐賀の農村風景を堪能して下さい。 続きを読む
さくら児童館からも撮り溜めた写真を、職員と、子ども達の写真の中から一枚ずつ出品していました。
その子ども達の写真が、「キッズ賞」に見事入選!

私は児童館に撮影に行った際には、子供たちに一眼レフカメラやビデオカメラを自由に使わせてみます。その場合には基本的な撮影方法だけ教えて、後は自由さえていて見ています。
この写真を撮ったのは女の子ですが、他の子どもに比べてセンスが良いなと常々思っていました。今回の写真を出品する際の選考に私うも立ち会ったのですが、この写真良いなと思い撮影者を聞いて「やっぱり」なと思った次第です。
この作品のタイトルは『そばの畑でかくれんぼ』ですが、多くの方が元ネタに気づかれたと思います。J・D・サリンジャーの『ライ麦畑でつかまえて』です。小説の内容と写真の状況は全く一致しませんが、大人たち全員がこのタイトルで納得してしまいました。子供ですから狙って撮った訳ではないでしょうが、先頭を歩いて来る男の子がイメージがぴったり過ぎて苦笑してしまいました。
入選作はモラージュ佐賀に08年12月末~09年1月上旬に展示されるそうですから、お暇の方は佐賀の農村風景を堪能して下さい。 続きを読む
「押し紙」って知っていますか?
販売店に持ち込まれる新聞は、配達時に新聞が濡れた時などに備える必要な「予備紙」が注文部数の2%まで認められているそうです。
しかし、実際にはそれを上回る(3~4割)もの配達されない新聞が持ち込まれいるとか。
これを「押し紙」と業界内では言うそうですが、新聞社は表向きには存在を認めていません。
この慣習はかなり昔から続いてようですが、要するに新聞社にとって、発行部数は広告を得るための重要な要素なのです。
広告主は多くの人に読まれている新聞に広告を載せたいと思います。
そのために部数を水増しして、見せ掛けの部数を増やしていたのです。
ただし、地方紙の場合、「押し紙」をしてでも大部数にみせかけ、広告の媒体価値を競い合う必要性は全国紙に比べて薄いようです。
そもそも販売店は新聞だけ配っていたのでは、儲けになりません。
新聞に差し込む折り込むチラシの収入で成り立っていました。
チラシの搬入枚数は、販売店が扱う新聞の総部数に準じるそうです。
部数が多いほどチラシ収入が多くなります。
また、新聞社が販売店へ補助金を支給していました。
つまりチラシの水増し収入と、押し紙で生じる損害を相殺するカラクリになっていました。
しかし、5~6年位前から様子が変わってきました。
新聞への広告掲載が減少してきたからです。
原因はダイレクトメール、フリーペーパーやインターネット広告にチラシの役割を奪われたからだと言われています。
また、広告主も新聞の広告効果に疑問を感じているようです。
それに、ニュースはTVとネットで十分だと考え、新聞を取らない人が増えれいます。
部数が減れば新聞社の販売店に対する補助金支給も、減っているのではないでしょうか。
これでは販売店はやって行けません。
自主廃業する販売店が増えたいます。
また「押し紙」の不公平さに対して訴訟を起こせケースも増えて、販売店が勝訴しているそうです。
この様な状況に対して新聞社も、新聞社側の資本も入った販売会社を増やして対抗しています。
しかし、現在のような販売店システムはこの先崩壊するのは目に見えています。
果たして、新聞社はどんな方策で生き残っていくのでしょうか?
山と積まれた配達されない新聞

販売店に持ち込まれる新聞は、配達時に新聞が濡れた時などに備える必要な「予備紙」が注文部数の2%まで認められているそうです。
しかし、実際にはそれを上回る(3~4割)もの配達されない新聞が持ち込まれいるとか。
これを「押し紙」と業界内では言うそうですが、新聞社は表向きには存在を認めていません。
この慣習はかなり昔から続いてようですが、要するに新聞社にとって、発行部数は広告を得るための重要な要素なのです。
広告主は多くの人に読まれている新聞に広告を載せたいと思います。
そのために部数を水増しして、見せ掛けの部数を増やしていたのです。
ただし、地方紙の場合、「押し紙」をしてでも大部数にみせかけ、広告の媒体価値を競い合う必要性は全国紙に比べて薄いようです。
そもそも販売店は新聞だけ配っていたのでは、儲けになりません。
新聞に差し込む折り込むチラシの収入で成り立っていました。
チラシの搬入枚数は、販売店が扱う新聞の総部数に準じるそうです。
部数が多いほどチラシ収入が多くなります。
また、新聞社が販売店へ補助金を支給していました。
つまりチラシの水増し収入と、押し紙で生じる損害を相殺するカラクリになっていました。
しかし、5~6年位前から様子が変わってきました。
新聞への広告掲載が減少してきたからです。
原因はダイレクトメール、フリーペーパーやインターネット広告にチラシの役割を奪われたからだと言われています。
また、広告主も新聞の広告効果に疑問を感じているようです。
それに、ニュースはTVとネットで十分だと考え、新聞を取らない人が増えれいます。
部数が減れば新聞社の販売店に対する補助金支給も、減っているのではないでしょうか。
これでは販売店はやって行けません。
自主廃業する販売店が増えたいます。
また「押し紙」の不公平さに対して訴訟を起こせケースも増えて、販売店が勝訴しているそうです。
この様な状況に対して新聞社も、新聞社側の資本も入った販売会社を増やして対抗しています。
しかし、現在のような販売店システムはこの先崩壊するのは目に見えています。
果たして、新聞社はどんな方策で生き残っていくのでしょうか?
山と積まれた配達されない新聞

2009年元旦
新年 明けまして、おめでとうございます。

本当は本物の初日の出の写真を貼りたかったのですが…。
生憎の曇天なので、これでご容赦下さい。
2009年一発目のブログは、アメリカ人の経済感覚が変わってきたと言うお話。
まー、この経済状況では変わらざろう得ませんが…。
でもこれって、普通の日本人の感覚ですよね。
その大量消費が世界経済を支えてきたとは言え、アメリカ人って本当に (-_-;)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
◎日経新聞(2008/12/28)
「倹約かっこいい」 米国流の消費、景気後退で変化
景気後退の影響が広がる米国社会で、倹約志向が高まりつつある。借金を重ねてモノを買い続けるという旧来のライフスタイルを見直し、カネをかけずとも、楽しく豊かに暮らす知恵に注目が集まっている。身の丈まで縮まってきた消費の現場を追った。
「今は倹約がかっこいいのよ」。大手IT(情報技術)企業に勤務するマリー・ホールさん(39)=ロサンゼルス市在住=から意外な言葉がもれた。有名デザイナーの服に身を包んでいるが、これらはサンプル品を格安で販売する特別セールや中古品専門店で購入したもの。自ら設定した月300ドル(約2万 7000円)の「おしゃれ予算」を守っている。
ホールさんの1日は新聞の折り込みチラシに目を通すことから始まる。店頭で割引券として使えるクーポンを収集。洋服から日用品、食品に至るまで、インターネットを使って価格を比較してから買い物をする。「(株式相場に連動した)企業年金は信用できない」と節約した金は貯金に回し、老後に備えている。
新年 明けまして、おめでとうございます。

本当は本物の初日の出の写真を貼りたかったのですが…。
生憎の曇天なので、これでご容赦下さい。
2009年一発目のブログは、アメリカ人の経済感覚が変わってきたと言うお話。
まー、この経済状況では変わらざろう得ませんが…。
でもこれって、普通の日本人の感覚ですよね。
その大量消費が世界経済を支えてきたとは言え、アメリカ人って本当に (-_-;)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
◎日経新聞(2008/12/28)
「倹約かっこいい」 米国流の消費、景気後退で変化
景気後退の影響が広がる米国社会で、倹約志向が高まりつつある。借金を重ねてモノを買い続けるという旧来のライフスタイルを見直し、カネをかけずとも、楽しく豊かに暮らす知恵に注目が集まっている。身の丈まで縮まってきた消費の現場を追った。
「今は倹約がかっこいいのよ」。大手IT(情報技術)企業に勤務するマリー・ホールさん(39)=ロサンゼルス市在住=から意外な言葉がもれた。有名デザイナーの服に身を包んでいるが、これらはサンプル品を格安で販売する特別セールや中古品専門店で購入したもの。自ら設定した月300ドル(約2万 7000円)の「おしゃれ予算」を守っている。
ホールさんの1日は新聞の折り込みチラシに目を通すことから始まる。店頭で割引券として使えるクーポンを収集。洋服から日用品、食品に至るまで、インターネットを使って価格を比較してから買い物をする。「(株式相場に連動した)企業年金は信用できない」と節約した金は貯金に回し、老後に備えている。